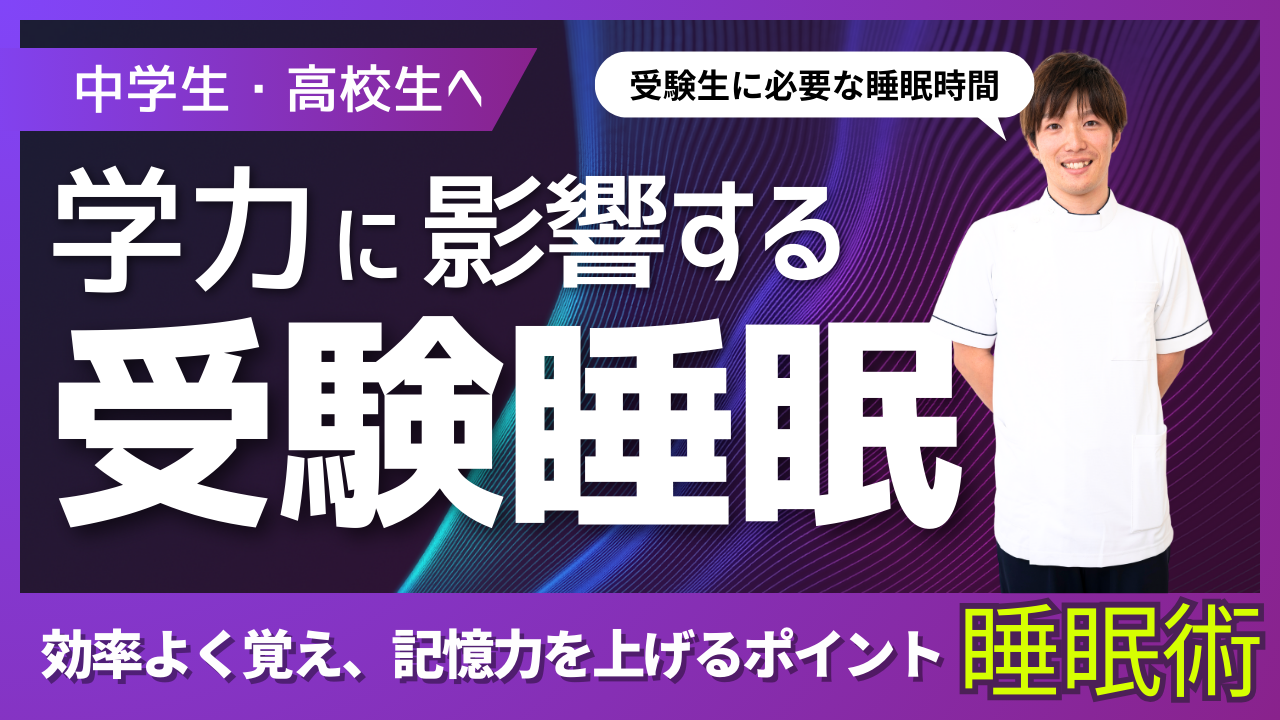目次
中・高校生に必要な睡眠時間の目安
成長期である中学生や高校生には 7~9時間の睡眠 が推奨されています。
特に脳が発達するこの時期は、深い睡眠(ノンレム睡眠)が新しい記憶の定着に重要な役割を果たします。
しかし、受験勉強やスマホの使用による夜更かしが習慣化し、平均睡眠時間が6時間以下になるケースが少なくありません。
ポイント
- 睡眠時間は量だけでなく、質も重要です。
- 生活リズムを整えることで、短時間でも深い睡眠が得られます。

睡眠不足が脳と学習に与える影響
睡眠不足は、脳の重要な部分である 前頭前野 や 海馬 の機能を低下させます。
特に次のような影響が顕著に現れます。
- 記憶力の低下: 学習した情報の整理が不十分になる。
- 集中力の低下: 勉強に集中する力が著しく低下し、効率が悪化する。
- 判断力の低下: テスト中の解答ミスやケアレスミスが増える。
科学的データ
米国スリープ財団の研究によると、睡眠が4時間以下になると、テスト成績が20%以上低下します。

受験生特有の問題と寝不足が原因
精神的ストレスの増加
睡眠不足は情緒を不安定にし、ストレス耐性を低下させます。
体調不良の増加
睡眠不足により免疫力が低下し、風邪や体調不良が起こりやすくなります。
パフォーマンスの低下
朝起きた時に頭がぼんやりして集中力が低下する「睡眠惰性」が強く現れます。
睡眠と記憶の関係 – 効率よく覚えるためのポイント
睡眠中、特にレム睡眠の間に記憶の整理や強化が行われます。夜に勉強したことは、睡眠を通してより深く記憶に刻まれます。
- 短い仮眠: 勉強後に20分の仮眠を取ることで、記憶の定着率が上がります。
- 夜の復習: 寝る前に暗記科目や重要なポイントを復習することで、記憶が強化されます。
時間帯別で効率が変わる!体内時計を活かした勉強法
「睡眠と記憶の関係」を理解したら、次に大切なのは“いつ勉強するか”という時間帯の工夫です。
人間の脳には体内時計(サーカディアンリズム)があり、集中力や記憶の定着しやすさは時間帯によって変わります。
ここでは、時間帯別におすすめの学習テクニックをご紹介します。
朝(起床直後~午前中):復習+新しい知識のインプット
起床後は脳が休息によってリフレッシュされ、記憶の整理が進んだ直後。
このタイミングでは、前日に覚えたことを軽く復習し、その後に新しい暗記や理解系の学習を取り入れるのが効果的です。
- 前夜に暗記した単語や公式を5〜10分で思い出す
- その後に新しい内容をインプットする
👉 まさに「忘却曲線」を防ぐ最適な時間帯です。
参考:Ebbinghausの忘却曲線研究
午前中:思考力が必要な勉強
午前中は前頭葉の働きが活発で、論理的思考や問題解決力が高まる時間帯です。
数学や理科の応用問題、作文や論述など「考える」勉強に取り組むと効率的です。
- 難しい問題を解く
- 「なぜそうなるのか」を自分の言葉で説明する
👉 脳が冴えている時間に“理解”を伴う勉強を。
午後(15〜17時):暗記や反復練習に最適
午後は一時的に集中力が落ちますが、15〜17時ごろは再び覚えやすさが高まる時間帯。
単語や歴史、用語などの暗記系を集中的に取り組むのに向いています。
- 短時間での暗記反復
- フラッシュカードやテスト形式で確認
👉 必要に応じて15〜20分のパワーナップ(仮眠)を活用すると効果UP。
参考:NASA仮眠研究(Napping improves alertness and performance, NASA Ames Research Center)
夜(寝る前1時間):暗記のゴールデンタイム
寝る直前に暗記した情報は、睡眠中の記憶固定(記憶の再編成)によって定着しやすいことがわかっています。
そのため、覚えたい重要ポイントを寝る直前に復習するのがおすすめです。
- 当日学んだ内容を要点だけ再確認
- 特に覚えたい単語や定義を繰り返す
👉 「寝る直前暗記 → 睡眠」で記憶の定着が最大化されます。
参考:Diekelmann & Born, 2010, Memory consolidation during sleep
深夜・徹夜は逆効果
徹夜勉強は一見“やった感”がありますが、実際には睡眠不足で脳の認知機能が低下し、翌日のパフォーマンスも落ちます。
大切なのは「勉強+睡眠」のセット。効率を考えるなら、徹夜は避けて睡眠を優先しましょう。
時間帯別・体内時計を味方につける記憶定着テクニック
| 時間帯 | 脳/記憶の特徴 | おすすめの学習タイプ | 活用テクニック例 |
|---|---|---|---|
| 起床直後~朝(起床後~2〜3時間) | 脳が休息後リフレッシュされており、新しい情報をインプットしやすい状態。 (学研のオンライン学習塾 学研オンエア) また、前夜に覚えた内容を思い出すと、忘却曲線を防ぐ復習効果が高まる。 (北摂セミナー | 大阪府高槻市の学習塾なら北摂セミナー) | 前夜の復習 → 新しい暗記・インプット | – 起床後すぐ5〜10分で、前夜に覚えた単語・公式・キーワードを思い出す(出力型復習) – その後、新しい内容を“少量ずつ”インプットする(30分程度) |
| 午前中・午前~昼過ぎ | 思考力・論理的判断力が高め(前頭葉の働きが比較的良好) | 理解系・思考系科目(数学・理科・作文など) | – 難しい問題・応用問題に取り組む – 問題を「なぜそうなるか」を自分で説明しながら解く |
| 午後(昼過ぎ〜夕方) | 午後に一時的な集中力の低下(いわゆる“落ちどき”)が起きやすい時間帯もあるが、15〜17時あたりは再び覚えやすさが上がるという指摘もあり。 (Takeda) | 暗記・反復演習 | – 午後15〜17時は暗記(単語・歴史・用語など)を集中的に行う – 午後の眠気に備えて、短時間仮眠(15〜30分)を活用する(ただし寝すぎ注意) |
| 夜~就寝前(寝る1〜2時間前) | 記憶の“固定化”を助けるプロセス(睡眠中の記憶統合)に近いため、寝る直前に暗記したことは定着しやすいという報告あり。 (日本の資格・検定|学びのメディア) | 暗記・総まとめ・重要ポイントの復習 | – 当日学んだ内容の要点を“5〜10分で再確認”(ノートやフラッシュカード) – 特に暗記すべき語句・定義・公式を寝る直前にリマインドする |
| 深夜・徹夜学習 | 睡眠剥奪状態では認知機能が落ち、記憶定着にとっては逆効果になることが多い | 極力避ける | 徹夜は極力避け、どうしても遅くなった場合は“寝る直前暗記 → 睡眠”を意識するようにする |

忙しい受験生のための睡眠の質を上げる4つのテクニック
①光をコントロールする
就寝1時間前はスマホやパソコンを避け、部屋を暗くすることで天然の睡眠薬と言われるホルモンのメラトニン分泌を促進します。
②ルーティンを決める
軽いストレッチやリラクゼーション音楽を聴くなど、寝る前のリラックス時間を作りましょう。
これをしたら眠れるというルーティンを持つと毎晩強いです。
③運動を取り入れる
日中に軽い運動をすることで、昼と夜の体温の変化が明確になり、深い睡眠を促します。
④寝室環境を整える
温度を18~22℃に保ち、季節に合わせた快適な寝具を使用します。寝具の素材は個人の好きな感触かどうかもポイントです。

睡眠に関するよくある誤解と正しい知識
誤解1: 睡眠を削れば勉強時間が増える
実際には学習効率が低下し、長期的には逆効果です。
誤解2: 昼寝は不要
短時間の昼寝は午後の集中力を高めます(20~30分推奨)。ぐっすり眠れなくても、脳が休憩できればオッケーです。
誤解3:睡眠時間が長い=怠けている
成長期には7~9時間の睡眠が必要であり、健康維持に不可欠です。

親や教師が知っておくべき受験生の睡眠サポート方法
親ができる具体的サポート
- 生活リズムを整える手助け: 家族全体で規則正しい生活を意識しましょう。
- ストレス軽減: プレッシャーをかけず、安心感を与える言葉をかけることが重要です。
教師ができる具体的サポート
- 睡眠の重要性を教える: 「睡眠も学習の一部」という考え方を生徒に伝えましょう。
- 個別対応: 睡眠不足が原因で成績が伸び悩む生徒には相談に乗り、適切なアドバイスを行います。
▼気になる記事7選▼
参考文献
- National Sleep Foundation (2020). Teens and Sleep. https://www.sleepfoundation.org
- 米国スリープ財団 (2020). 睡眠不足が認知能力に与える影響に関する研究。
- Carskadon, M. A. (1990). Patterns of Sleep and Sleepiness in Adolescents. Journal of Adolescent Health.
- 厚生労働省 (2023). 健康づくりのための睡眠指針 2023年改訂版.