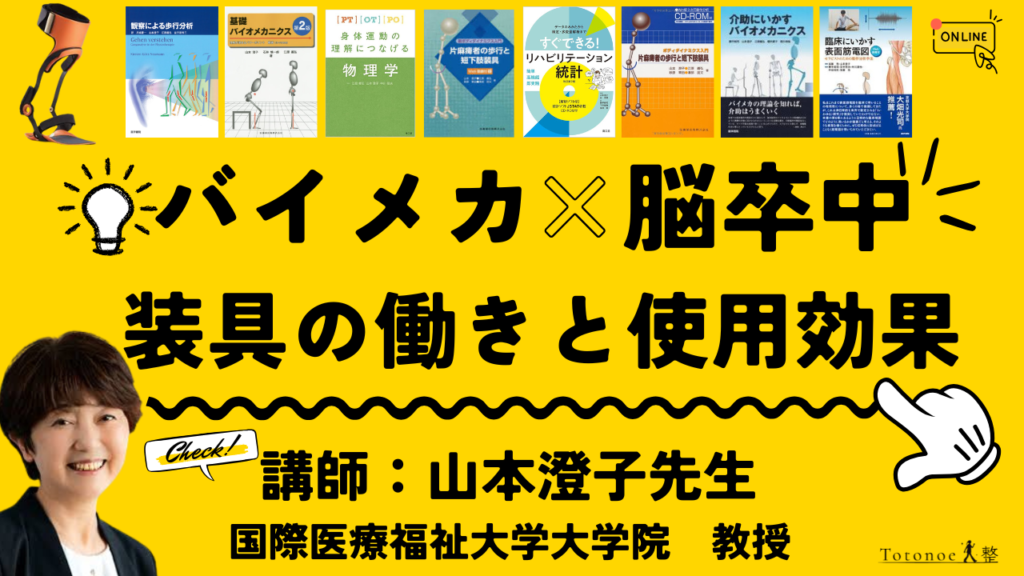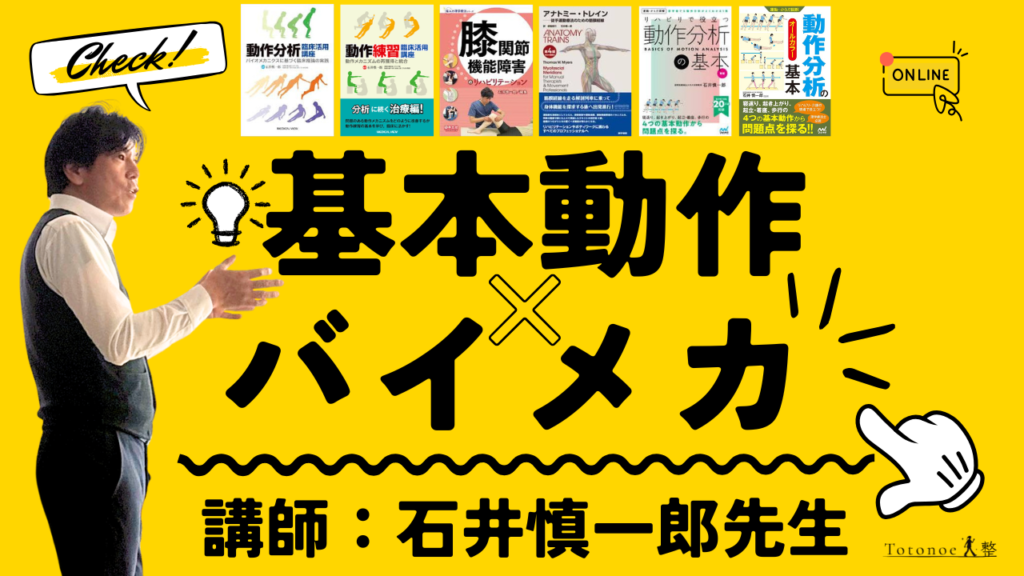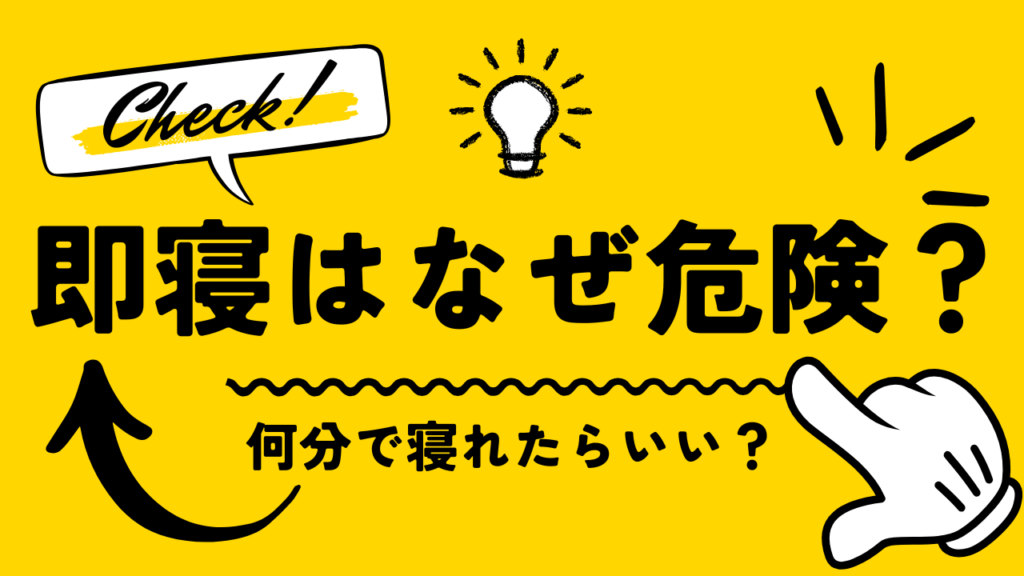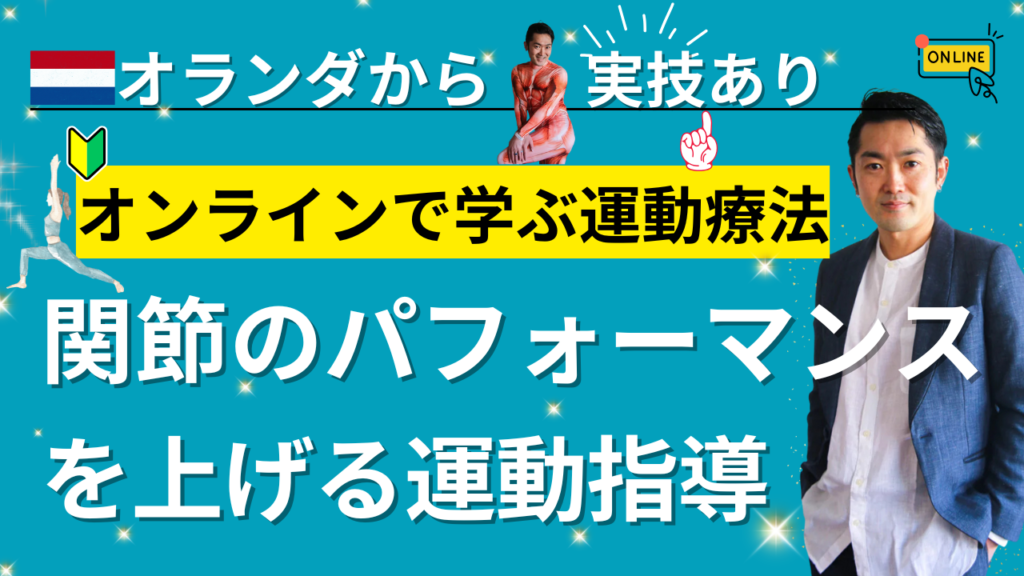顎が痛い、口が開けにくい、耳の近くで不快な音がする――
これらの症状に悩まされている方々の中には、歯ぎしりが原因であることが少なくありません。
歯ぎしりは、医学的には「ブラキシズム」と呼ばれ、顎関節症(TMJ症候群)を引き起こす主な要因の一つです。
本記事では、顎関節症の原因としての歯ぎしりについて、睡眠オタクな作業療法士の視点から専門的に解説します。

顎関節症とは?
顎関節症(Temporomandibular Joint Disorder, TMJ)は、顎関節や周囲の筋肉に問題が生じることで発症する疾患です。主な症状には、以下のようなものがあります。
- 顎の痛みやこり
- 顎を動かすときの音(クリック音やクラック音)
- 口が開けにくい、または閉じにくい
- 顎の運動制限
- 頭痛、耳痛、肩こり
顎関節症は、原因が多岐にわたる複雑な疾患ですが、その一つに歯ぎしりが挙げられます。
歯ぎしりとは?
歯ぎしり(ブラキシズム)は、無意識のうちに上下の歯を擦り合わせたり、噛み締めたりする行動を指します。睡眠中に起こることが多いため、本人が気づかないうちに症状が進行することがあります。
ブラキシズムの種類
- 睡眠時ブラキシズム:夜間に起こる歯ぎしりで、ストレスや不安、睡眠障害が原因となることが多いです。
- 覚醒時ブラキシズム:日中の無意識の歯ぎしりで、集中しているときや緊張しているときに起こりやすいです。
歯ぎしりが顎関節症を引き起こすメカニズム
歯ぎしりが顎関節症を引き起こす具体的なメカニズムについては、以下の要因が関与しています。
筋肉への負荷
歯ぎしりは、咀嚼筋(咬筋、側頭筋など)に過剰な負荷をかけます。これにより、筋肉が疲労し、緊張が続くことで筋肉痛やこりが発生します。
また、筋肉の緊張は顎関節にも影響を及ぼし、痛みや運動制限を引き起こします。
関節への圧力
歯ぎしりは、顎関節にも過度の圧力をかけます。長時間にわたる圧力が加わることで、関節の軟骨が摩耗し、炎症が生じます。これが関節痛やクリック音の原因となります。
歯の損傷
歯ぎしりは、歯の表面を摩耗させ、歯のエナメル質を損傷します。歯が摩耗すると、咬合(噛み合わせ)が乱れ、これがさらに顎関節に負担をかける悪循環を生み出します。
▼夜中に歯を強く噛む癖の改善方法▼
歯ぎしりの診断と治療
歯ぎしりが顎関節症の原因と疑われる場合、適切な診断と治療が重要です。
診断
- 自己報告:歯ぎしりの症状に気づいている場合、その頻度や時間帯を記録します。
- 歯科検診:歯科医が歯の摩耗や咬合の乱れをチェックします。
- 筋電図(EMG):咀嚼筋の活動を測定し、筋肉の緊張状態を評価します。
- ポリソムノグラフィー:睡眠時の歯ぎしりの有無を確認するための睡眠検査です。
治療
- ナイトガードの使用:睡眠時にナイトガードを装着することで、歯ぎしりによる歯の摩耗や顎関節への負荷を軽減します。
- ストレス管理:ストレスや不安が歯ぎしりの原因となる場合、リラクゼーション法や心理療法を取り入れることが有効です。
- 薬物療法:痛みや炎症を軽減するために、抗炎症薬や筋弛緩薬が処方されることがあります。
- 理学療法:作業療法士や理学療法士が指導するエクササイズやマッサージが、筋肉の緊張をほぐし、顎の機能を改善します。
予防とライフスタイルの改善
顎関節症の予防と症状の軽減には、ライフスタイルの改善が欠かせません。
ストレス管理
ストレスは歯ぎしりの大きな原因の一つです。ヨガや瞑想、深呼吸法などのリラクゼーション技法を取り入れることで、心身の緊張を緩和します。
適切な睡眠環境
良質な睡眠によって、ストレス軽減や歯への負担を軽減するために、以下のポイントに注意しましょう。
- 快適なマットレスと枕の選択
- 寝室の温度や湿度の調整
- 寝る前の電子機器の使用を控える
定期的な歯科検診
定期的に歯科医の診察を受けることで、早期に歯ぎしりの兆候を発見し、適切な対策を講じることができます。

\ 最新の記事をスワイプ👆⇒ /
なぜ睡眠薬を飲み続けても不眠は治らないのか?|効かない本当の理由を作業療法士が解説
保護中: 山本澄子先生セミナー受講生専用 ※3/31まで
保護中: 石井慎一郎先生セミナー受講生専用 ※3/31まで
布団に入ってすぐ寝る人は要注意?「即寝」がよくない本当の理由を医療視点で解説
【オンラインで学ぶ運動療法】関節のパフォーマンスを上げる運動指導
正常運動と異常運動を「体感」して、明日から“説明して介入できる”PTへ こちらはオンラインセミナーのご案内になります。 対象は、 理学療法士・作業療法士 運動療法に携わる方 初心者大歓迎 こんな方にお…
運動と睡眠は切り離せない。 機能改善の鍵は“関係性”にあった。PT/OT向けセミナー
こちらの記事は ・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 対象となるオンラインセミナーのご案内です。 ●こんな悩みありませんか? ☑寝不足でパフォーマンスが安定しないクライアントがいる☑運動指導しても…

結論
歯ぎしりが引き起こす顎関節症は、適切な診断と治療によって改善が期待できます。ストレス管理や睡眠環境の整備、定期的な歯科検診など、日常生活の中でできる対策を積極的に取り入れましょう。
顎の痛みや不快な症状に悩まされることなく、健やかな生活を送るために、専門的な知識を持った医療従事者に相談することをお勧めします。
よくある質問
質問1: 顎関節症の予防には、どのようなエクササイズが有効ですか?
回答1: 顎関節症の予防には、顎のストレッチや筋肉の強化が重要です。例えば、口を大きく開けて閉じる運動や、顎を左右にゆっくり動かすエクササイズが効果的です。
これにより、咀嚼筋の柔軟性が向上し、顎関節への負担が軽減されます。また、作業療法士が指導する特定の筋力強化運動も有用です。
質問2: 歯ぎしりが原因で歯が摩耗した場合、どのような治療法がありますか?
回答2: 歯ぎしりによる歯の摩耗が進行した場合、歯科医はコンポジットレジンやセラミッククラウンを使用して歯を修復します。また、歯ぎしりを防ぐためのナイトガードの装着も推奨されます。これにより、さらに歯が摩耗するのを防ぎ、咬合の安定性が向上します。
質問3: 顎関節症と診断された場合、どのような生活習慣の改善が推奨されますか?
回答3: 顎関節症と診断された場合、食生活の改善が重要です。硬い食べ物やガムを避け、柔らかい食べ物を摂取することが推奨されます。
また、ストレス管理も重要で、瞑想や深呼吸、リラクゼーション法を取り入れることが有効です。さらに、睡眠時の姿勢にも注意し、仰向けで寝るように心がけることが大切です。
質問4: 顎関節症の手術治療はどのような場合に行われますか?
回答4: 顎関節症の手術治療は、保存療法が効果を示さない重症例や、顎関節の構造的な異常が原因である場合に考慮されます。関節鏡視下手術や関節整形術が代表的な手術法です。
これらの手術は、関節の炎症を取り除き、構造的な問題を修正することを目的としています。
質問5: 歯ぎしりによる顎関節症のリスクを減らすために、日常的にできることはありますか?
回答5: 歯ぎしりによる顎関節症のリスクを減らすためには、日常生活でのストレス管理が重要です。ヨガや瞑想、定期的な運動を取り入れることでストレスを軽減できます。
また、睡眠環境の改善も大切で、適切な枕やマットレスを使用し、快適な睡眠を確保することが推奨されます。さらに、定期的な歯科検診を受けることで早期に問題を発見し、対策を講じることができます。
▼「歯」と睡眠シリーズ▼

\書籍はWEBで購入可/

\睡眠オタのYouTubeチャンネル/

\どんな活動してるの?/

引用文献
- American Academy of Orofacial Pain. “Guidelines for Assessment, Diagnosis, and Management.” 6th edition.
- Okeson, J. P. (2019). Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion. 8th edition. Elsevier.
- Lavigne, G. J., Khoury, S., Abe, S., Yamaguchi, T., & Raphael, K. (2008). Bruxism physiology and pathology: an overview for clinicians. Journal of Oral Rehabilitation, 35(7), 476-494.
- de Leeuw, R., & Klasser, G. D. (2013). Orofacial Pain: Guidelines for Assessment, Diagnosis, and Management. Quintessence Publishing Co, Inc.