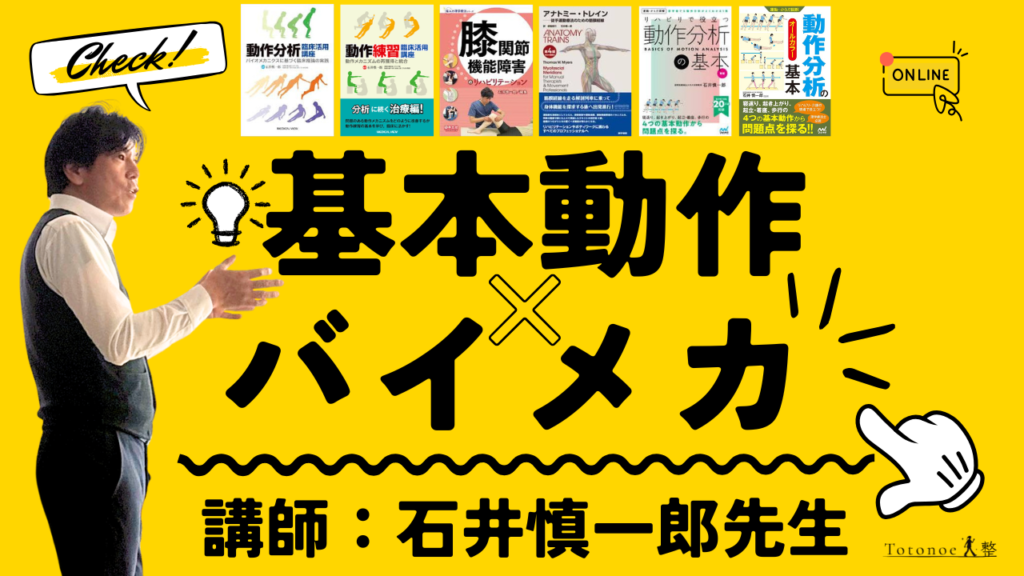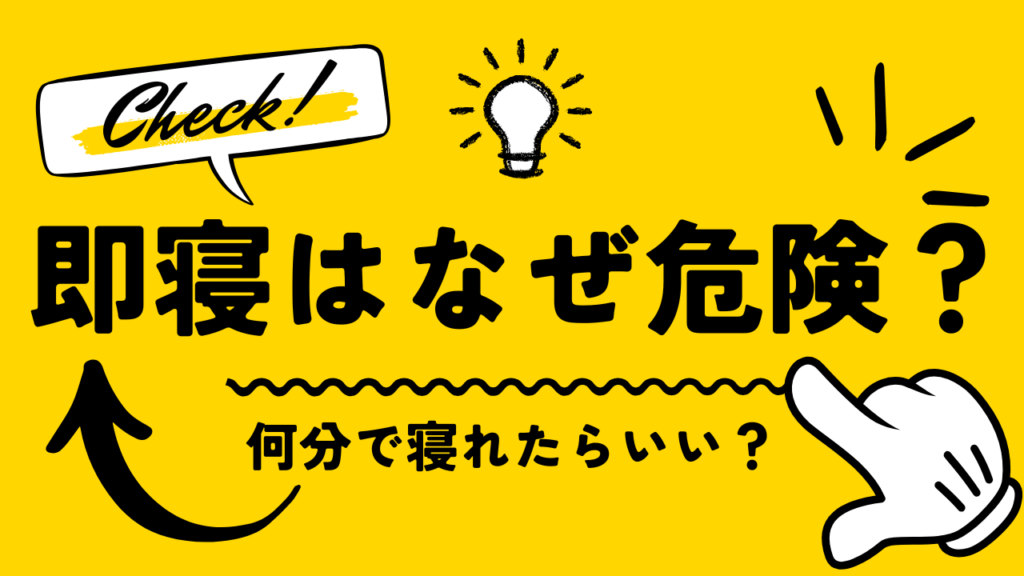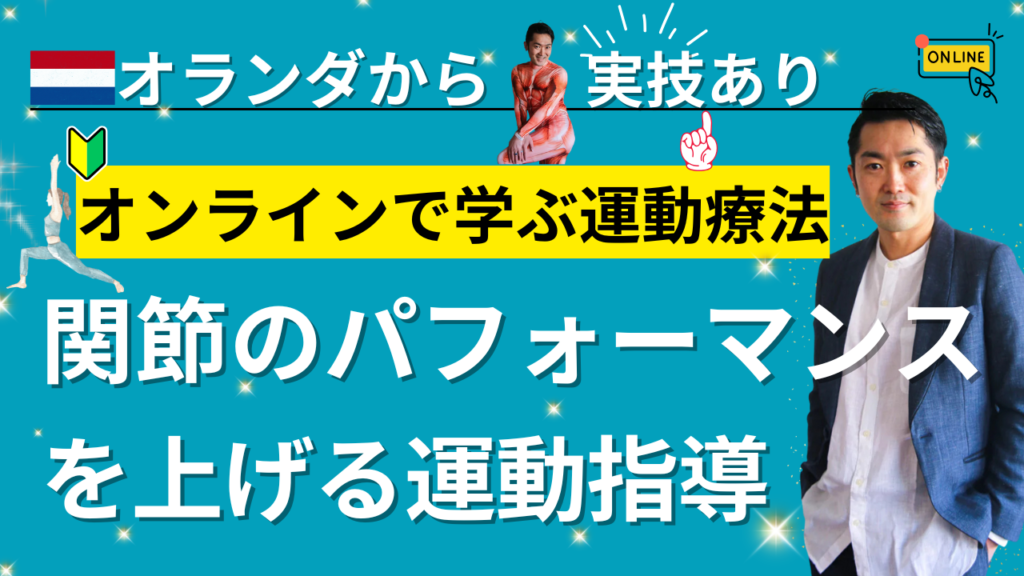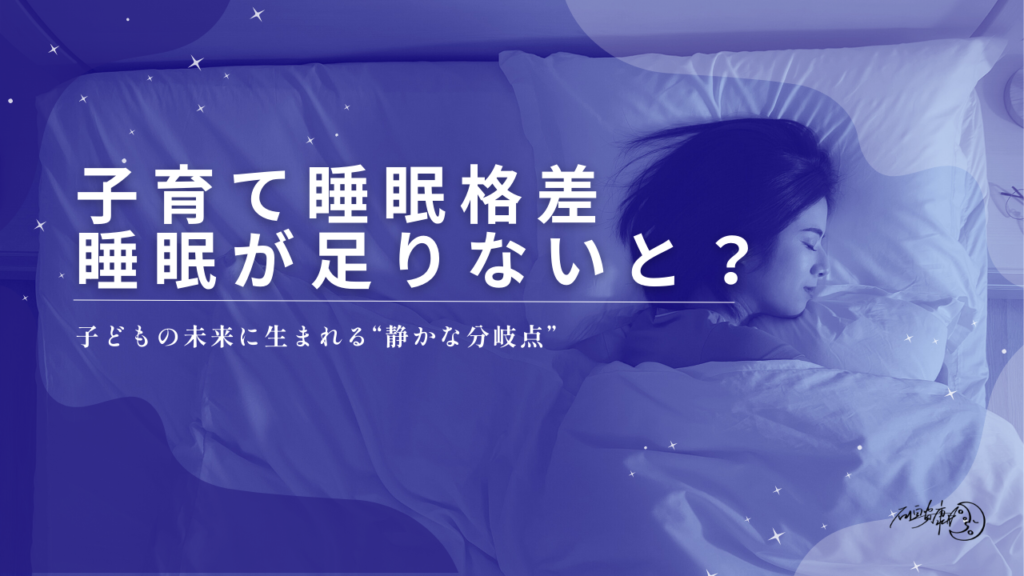目次
はじめに
夜中に頻繁に目が覚めて水を飲むことは、多くの人々にとって日常的な問題です。
この行動は睡眠の質に直接的な影響を及ぼすだけでなく、根本的な健康問題の兆候である可能性もあります。
本記事では、睡眠オタクな作業療法士としての視点から、夜中に水を飲む頻度が多い人々へのアドバイスを提供します。
医療用語を交えながら、より専門的な内容を目指します。

「水と睡眠」簡易テスト
▼「はい」の数を数えましょう▼
| チェック項目 |
|---|
| 夜中に2回以上水を飲むことがある |
| 就寝前にカフェインやアルコールを摂取することが多い |
| 夜中に目が覚めるたびにトイレに行く |
| 朝起きたときに疲労感が残っている |
| 夕方以降に大量の水分を摂取している |
スコア
| 合計スコア | 評価 |
|---|---|
| 0-1 | 問題なし |
| 2-3 | 注意が必要 |
| 4-5 | 対策が必要(専門医に相談を推奨) |
夜間の水分摂取の影響
夜中に水を飲む頻度が高いと、睡眠の連続性が断たれ、深い睡眠段階(REMおよびNREM)の持続時間が短くなります。
これにより、睡眠の質が低下し、日中の疲労感や集中力の欠如などが生じます。
また、頻繁な起床は膀胱の過敏症や夜間頻尿(Nocturia)の原因にもなります。

夜間頻尿の原因と対策
①原因
- 多尿:夜間に尿量が増える状態で、慢性腎疾患や糖尿病、心不全などが原因となることがあります。
- 膀胱容量の減少:加齢や膀胱過活動症(Overactive Bladder)によって膀胱の容量が減少し、頻繁にトイレに行く必要が生じます。
- 飲料習慣:就寝前に大量の水分を摂取することが直接的な原因となることが多いです。
②対策
- 夕方以降の水分摂取制限:就寝の3〜4時間前から水分摂取を控えるようにします。
- カフェインとアルコールの摂取制限:これらの飲料は利尿作用があり、夜間の尿意を増やす可能性があります。
- 膀胱訓練:排尿の間隔を徐々に延ばす訓練を行い、膀胱の容量を増やすことを目指します。
- 医療機関での相談:夜間頻尿が続く場合は、泌尿器科専門医に相談し、適切な治療を受けることが重要です。

適切な睡眠環境の整備
夜間の水分摂取を減少させるためには、適切な睡眠環境の整備も重要です。
- 適切な温度と湿度:室温は16〜18℃、湿度は40〜60%を保つようにします。
- 適切なマットレスと枕の選定:体圧分散に優れたマットレスや、自分の体型に合った枕を選び、快適な睡眠環境を整えます。
- 光の管理:就寝前に明るい光を避け、暗く静かな環境を整えることで、メラトニンの分泌を促進し、自然な眠りをサポートします。
▼「寝室環境」についてオススメ記事▼
ライフスタイルの見直し
夜中に水を飲む頻度が多い場合、ライフスタイルの見直しも有効です。
- 食事の管理:塩分の摂取量を減らし、バランスの取れた食事を心がけます。高塩分の食事は体液量を増やし、尿量の増加を引き起こす可能性があります。
- 定期的な運動:適度な運動は全身の血行を促進し、膀胱の機能を改善する効果があります。ただし、就寝前の過度な運動は逆効果となるため、注意が必要です。
- ストレス管理:ストレスは夜間の覚醒を引き起こす要因の一つです。リラクゼーション法や深呼吸、ヨガなどを取り入れ、心身のリラックスを図ります。
▼[現代生活が睡眠の質を下げる]記事▼
医療的なアプローチ
夜中に頻繁に水を飲むことが続く場合、医療的なアプローチが必要になることがあります。
- 検査と診断:尿検査や血液検査、睡眠検査(ポリソムノグラフィー)を通じて、根本的な原因を特定します。
- 薬物療法:必要に応じて、利尿剤や抗コリン薬などの薬物療法が検討されます。
- 行動療法:膀胱訓練や夜間の排尿パターンの変更を支援する行動療法が行われることがあります。
▼2026年!「お伊勢さん」特別企画!!▼


\ 最新の記事をスワイプ👆⇒ /
保護中: 石井慎一郎先生セミナー受講生専用
布団に入ってすぐ寝る人は要注意?「即寝」がよくない本当の理由を医療視点で解説
【オンラインで学ぶ運動療法】関節のパフォーマンスを上げる運動指導
正常運動と異常運動を「体感」して、明日から“説明して介入できる”PTへ こちらはオンラインセミナーのご案内になります。 対象は、 理学療法士・作業療法士 運動療法に携わる方 初心者大歓迎 こんな方にお…
運動と睡眠は切り離せない。 機能改善の鍵は“関係性”にあった。PT/OT向けセミナー
こちらの記事は ・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 対象となるオンラインセミナーのご案内です。 ●こんな悩みありませんか? ☑寝不足でパフォーマンスが安定しないクライアントがいる☑運動指導しても…
寝不足で育つ子の見えない格差|睡眠時間が足りないと何が起きる?子どもの未来に生まれる“静かな分岐点”
【リハ職向け】予防視点のリハ睡眠──施術効果が続く身体づくりのためにできること──
🔍こんな悩み、ありませんか? ☑ 施術・トレーニング後は良いのに、すぐ元に戻る人がいる☑ 可動域や動作の改善が、翌日には低下してしまうことがある☑睡眠ってそもそもどう評価していいかわからない☑ 睡眠の…

結論
夜中に頻繁に水を飲むことは、単なる習慣ではなく、潜在的な健康問題の兆候であることが少なくありません。
適切な生活習慣の見直しや医療的なアプローチを通じて、この問題に対処することが重要です。
自分の体のサインを見逃さず、適切な対策を講じることで、より質の高い睡眠を手に入れましょう。
▼入院患者さんの夜間頻回トイレについて▼
よくある質問とそれに対する回答
質問1: 夜間頻尿は年齢と関係がありますか?
加齢は夜間頻尿の重要な要因の一つです。年齢と共に膀胱の筋肉が弱くなり、膀胱の容量が減少するため、頻繁に排尿が必要になります。
また、ホルモンバランスの変化も影響を及ぼします。高齢者では特に抗利尿ホルモン(ADH)の分泌が低下し、夜間の尿量が増えることがあります。
質問2: 夜中に起きて水を飲むときの適切な水分量はどれくらいですか?
夜中に起きて水を飲む場合、適量は一度に50〜100ml程度が推奨されます。
大量に飲むと膀胱に負担がかかり、さらに頻繁な起床を招く可能性があります。水分補給は重要ですが、適量を守ることが大切です。
質問3: 夜間頻尿に対する薬物療法にはどのようなものがありますか?
夜間頻尿の薬物療法としては、抗コリン薬やβ3アドレナリン受容体作動薬が一般的に使用されます。
抗コリン薬は膀胱の過活動を抑制し、尿意を減少させます。
β3アドレナリン受容体作動薬は膀胱の筋肉を弛緩させ、膀胱容量を増やします。医師の指導のもとで適切な治療を受けることが重要です。
質問4: 食事が夜間頻尿に与える影響について教えてください。
食事は夜間頻尿に大きな影響を与えます。
特に塩分やカフェイン、アルコールを含む食事は利尿作用があり、夜間の尿量を増やす可能性があります。
塩分の摂取量を減らし、カフェインやアルコールを控えることが夜間頻尿の改善に役立ちます。また、夕食の時間を早めることも効果的です。
質問5: 夜間頻尿のために推奨される運動やエクササイズはありますか?
夜間頻尿の改善には、骨盤底筋群の強化を目的としたケーゲル運動が推奨されます。
これにより、膀胱の支持構造を強化し、尿意のコントロールが向上します。
また、全身の血行を促進する有酸素運動(ウォーキング、サイクリングなど)も膀胱機能の改善に役立ちます。定期的な運動は全体的な健康にも良い影響を与えます。
▼睡眠オタOTオススメ記事3選▼

\書籍はWEBで購入可/

\睡眠オタのYouTubeチャンネル/

\どんな活動してるの?/

引用文献
- National Institute on Aging. (2020). Bladder Health. Retrieved from https://www.nia.nih.gov/health/bladder-health
- American Urological Association. (2021). Nocturia. Retrieved from https://www.auanet.org/guidelines/nocturia-guideline
- Mayo Clinic. (2022). Overactive Bladder. Retrieved from https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/overactive-bladder/symptoms-causes/syc-20355714
- National Sleep Foundation. (2023). Sleep and Hydration. Retrieved from https://www.sleepfoundation.org/nutrition/hydration