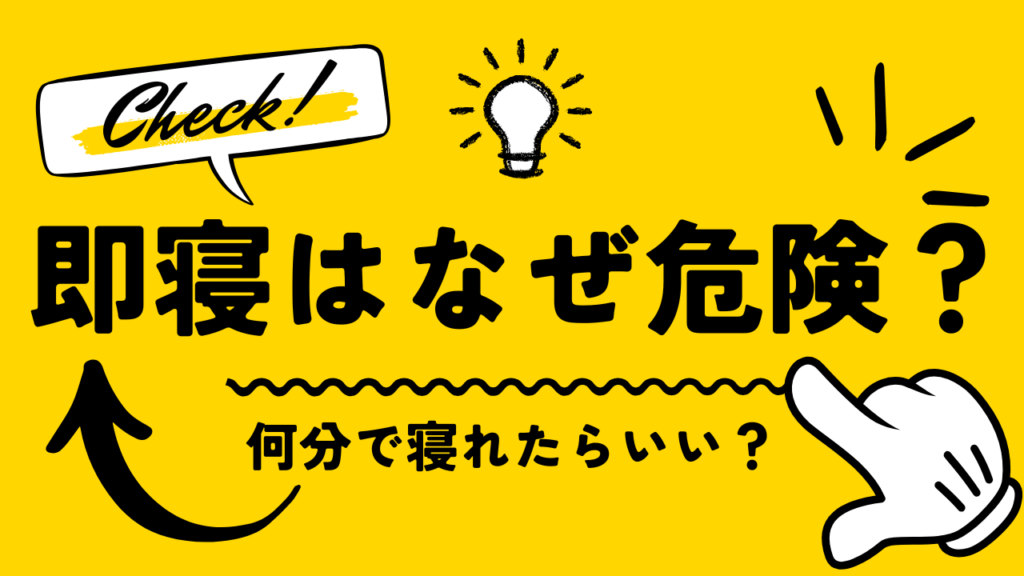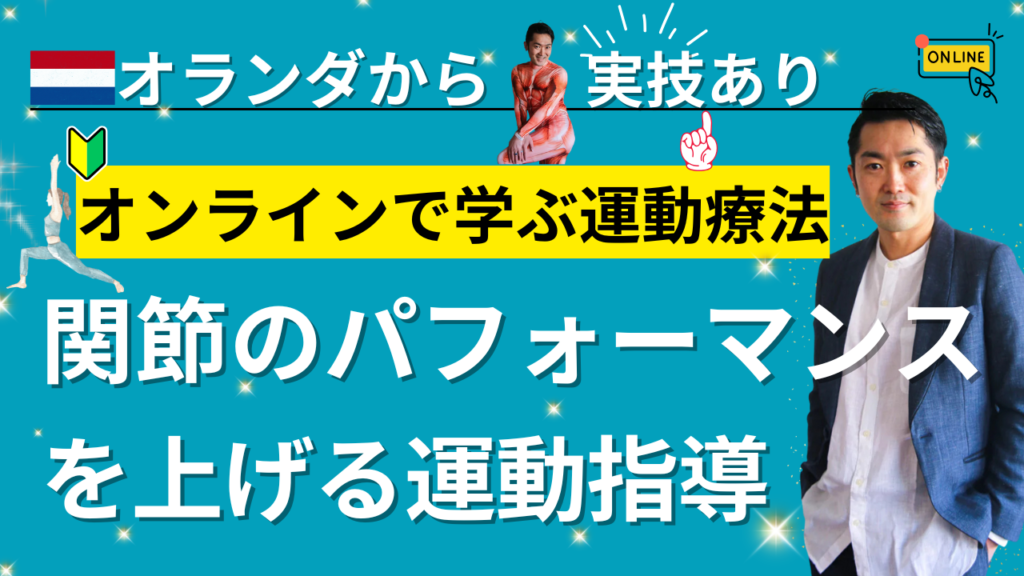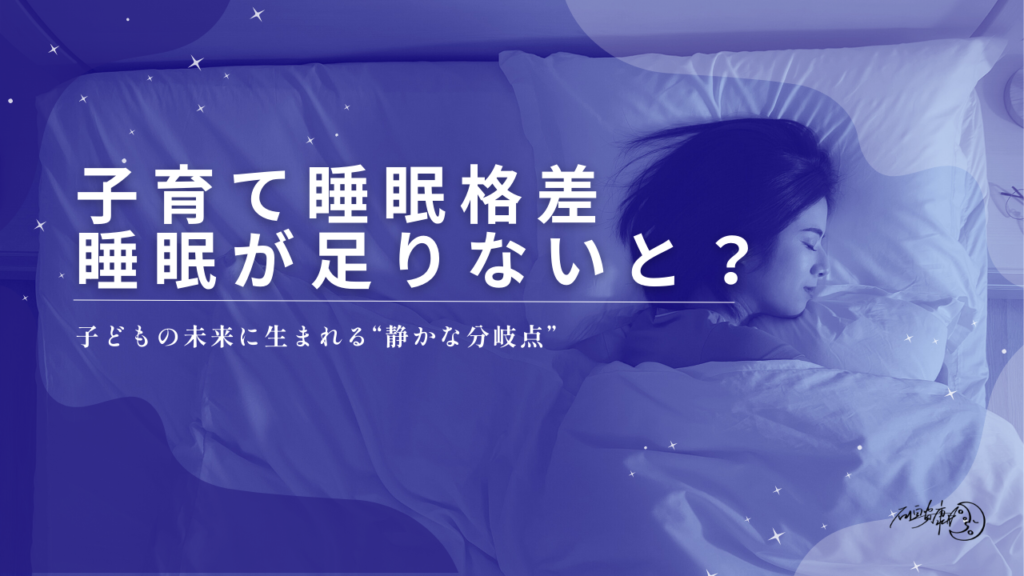目次
はじめに:こんな不合理、あなたにも心当たりありませんか?
- 明日早いのに、なぜか夜ふかししてしまう…
- スマホが睡眠によくないのは知ってるのに、つい手が伸びる…
- 昼間「今日は絶対に早く寝るぞ」と思っていたのに、夜になるとその意志が崩壊…
実はこれ、「あなたが意志が弱いから」ではありません。
むしろ、人間の脳の“当たり前の性質”とも言える不合理さが、睡眠に深く関わっているのです。
本記事では、「人間の不合理な行動」と「睡眠の科学」がどう関係しているのか、そしてそれをどう活かして“逆に”眠りを整えるのかを、医療職かつ睡眠オタクの視点で解説していきます。

人はなぜ“不合理”な選択をしてしまうのか?
「合理的に動けない脳」の仕組み
人間の脳は、主に2つのシステムで意思決定をしています。
- システム1=直感・感情・過去の経験に基づいた自動思考
- システム2=理性・論理・意志力を使った思考
行動経済学者ダニエル・カーネマンが提唱したこのモデルは、日常生活の「非合理性」の多くを説明してくれます。
睡眠においても、「わかっていても寝られない」の多くはシステム1の暴走が原因です。
夜になると「理性が弱まる」脳の時間帯特性
前頭前野(理性的判断を担う部位)は、夜になると活動が低下し、「感情」や「快楽」に弱くなることがわかっています(Killgore, 2010)。
つまり、理性的に「早く寝よう」と決めたとしても、夜の脳は誘惑に負けやすくなってしまうのです。
睡眠不足で“判断力”がそもそも崩れる
睡眠不足は「自己制御能力(self-control)」を低下させます(Pilcher & Huffcutt, 1996)。
それにより、人はより短期的な報酬(SNSの快楽、深夜のラーメンなど)に流されやすくなります。
つまり「寝不足=さらに寝づらくなる」悪循環が、ここに生まれます。

不合理さと“睡眠習慣”の関係性
なぜ「夜ふかしがやめられない」のか?
以下のような行動パターン、ありませんか?
- やるべきことが終わってからが「自分時間」になる
- SNSや動画視聴が“報酬”として働く
- 「今日はもうダメだったし、明日からでいいや」という思考
これは心理学で「報酬遅延割引(Delay Discounting)」と呼ばれ、将来の健康(良い睡眠)よりも、今すぐの快楽(スマホなど)を選ぶ傾向のことです。
しかも、睡眠不足になるとこの傾向がさらに強くなることもわかっています。
“リベンジ夜ふかし”に潜む心理とは?
「リベンジ夜ふかし(revenge bedtime procrastination)」とは、日中にコントロールできなかった生活への“反発”として、夜に自由時間を確保しようとする現象です(Kroese et al., 2014)。
例えば…
- 忙しくて自分の時間がなかった
- 嫌なことばかりの一日だった
こうした「報われなさ」への逆襲として、私たちは“夜に自由を取り戻す”かのように寝る時間を削ってしまうのです。
人はなぜ「睡眠を軽視する」のか?
「眠れなくても大丈夫」という“誤認”
睡眠不足によるパフォーマンス低下は、自覚しにくい特性があります。
Van Dongenらの研究(2003)によれば、睡眠時間が6時間以下になると認知機能が大きく低下するにもかかわらず、本人の自覚はあまりない。
つまり、眠れていないことにすら気づけない。
「将来の自分」への無関心(時間的視野の狭さ)
私たちは「未来の健康」よりも「今日の満足」に価値を感じやすい。
これは時間的視野(Time Perspective)の偏りで、未来志向が低いほど睡眠習慣は乱れやすい傾向があります(Zimbardo & Boyd, 1999)。
睡眠改善に“合理性”を求めないアプローチ
睡眠改善に必要なのは“行動設計”
普段私のところに相談来られる方には、睡眠の質を上げるには「意志の力」よりも、「環境と習慣の設計」が大事とお伝えしております。
「よし!今日は寝る!」ではない。
「眠りをマネジメントしましょう!」
以下は、“合理的に眠れない脳”を前提にした設計戦略です。
| 戦略 | 具体策 |
|---|---|
| 誘惑排除 | 寝室にスマホを持ち込まない/物理的に遠ざける |
| 環境制御 | 21時以降は照明を暖色に/音楽もリラックス系に |
| 習慣化 | 「眠るための儀式」(歯磨き→ストレッチ→読書)を固定する |
| 先に決める | 22時に自動的にスマホのWi-FiをOFFにする設定にしておく |
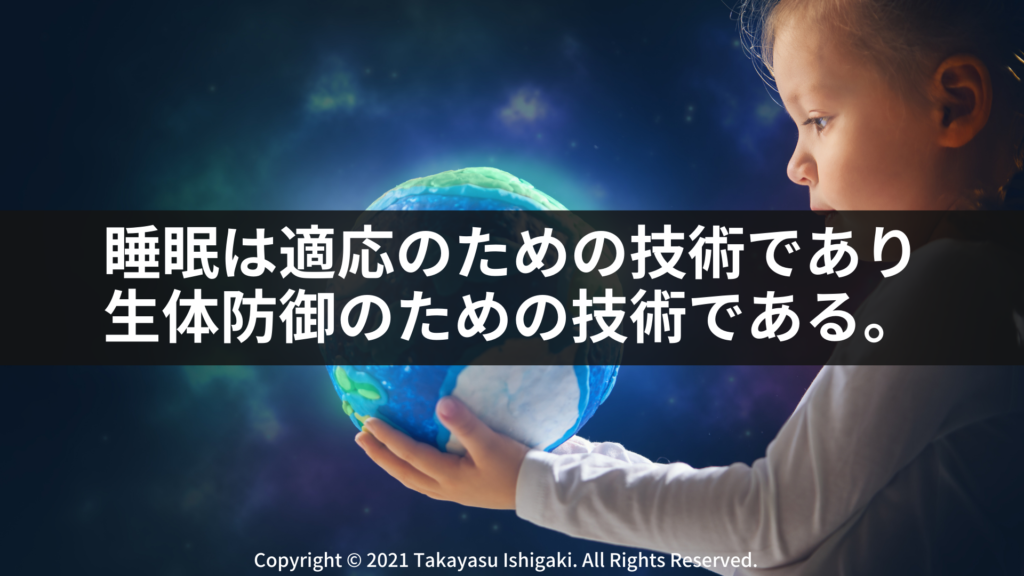
「感情」を味方にする
人間は論理よりも「感情」で動く生き物。
だからこそ、“感情的メリット”を意識することが有効です。
- 「ちゃんと眠れた日の朝はこんなに気持ちいい!」
- 「寝不足の日は顔もむくむし、気分も落ち込む…」
快と不快を“見える化”して、感情に訴えると行動が変わりやすくなります。
「非合理」な人間を前提とした睡眠習慣の作り方
行動経済学を活用した「ナッジ設計」
行動経済学の“ナッジ理論”を使えば、自然と眠りやすい行動に導くことができます。
- アラームを「起きる時間」ではなく「寝る時間」に設定
- ベッドに入ると自然と眠れるよう“照明・香り・音”をデザイン
- 寝室に「スマホNG」や「入眠30分前ルール」の掲示物を貼る
“自己責め”から“仕組み改善”へ
「わたしは意志が弱い」
「今日もダメだった…」
こんなふうに自己否定するのは逆効果。
重要なのは、【自分の脳は不合理である】と前提を持ち、責めるのではなく「仕組みを変える」ことです。
▼気になる記事3選▼
OT視点でのアプローチ|習慣療法
作業療法士としての立場からは、「生活マネジメントの乱れ」や「自己効力感の低下」が睡眠障害の背景にあることも多く見てきました。
- 昼間の活動に意味が見いだせない(ワーカホリズムや退職後の無気力)
- “眠る”という行為に満足感がない(快の蓄積が不足)無関心、価値が低い
- 生活全体のリズム設計が本人に合っていない
そこで有効なのが、「習慣療法(Habit Training)」や「作業スケジューリング」によるアプローチです。
▼2026年!「お伊勢さん」特別企画!!▼


\ 最新の記事をスワイプ👆⇒ /
布団に入ってすぐ寝る人は要注意?「即寝」がよくない本当の理由を医療視点で解説
【オンラインで学ぶ運動療法】関節のパフォーマンスを上げる運動指導
正常運動と異常運動を「体感」して、明日から“説明して介入できる”PTへ こちらはオンラインセミナーのご案内になります。 対象は、 理学療法士・作業療法士 運動療法に携わる方 初心者大歓迎 こんな方にお…
運動と睡眠は切り離せない。 機能改善の鍵は“関係性”にあった。PT/OT向けセミナー
こちらの記事は ・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 対象となるオンラインセミナーのご案内です。 ●こんな悩みありませんか? ☑寝不足でパフォーマンスが安定しないクライアントがいる☑運動指導しても…
寝不足で育つ子の見えない格差|睡眠時間が足りないと何が起きる?子どもの未来に生まれる“静かな分岐点”
【リハ職向け】予防視点のリハ睡眠──施術効果が続く身体づくりのためにできること──
🔍こんな悩み、ありませんか? ☑ 施術・トレーニング後は良いのに、すぐ元に戻る人がいる☑ 可動域や動作の改善が、翌日には低下してしまうことがある☑睡眠ってそもそもどう評価していいかわからない☑ 睡眠の…
ノンレム睡眠からステージ4が消えた理由|深睡眠は減った?分類変更を科学的に解説

まとめ|人は不合理だからこそ、工夫できる
合理的じゃないのが人間。
でも、それを「前提」にして工夫すれば、
“自然に眠れる仕組み”を誰でも作ることができます。
最後に、今日からできる“3つの最初の一歩”を紹介します。
- 寝る1時間前に「スマホを物理的に遠ざける」
- 「寝る前の儀式(ルーティン)」を3ステップで決める
- 寝不足の翌朝の“不快”を記録する(日記orメモ)
このブログ記事が面白いと思った方はポジティブシェアして、アウトプットにご協力いただけると嬉しいですm(_ _)m
どうか、たくさんの方に届きますように。
▼2026年!「お伊勢さん」特別企画!!▼


\ 最新の記事をスワイプ👆⇒ /
布団に入ってすぐ寝る人は要注意?「即寝」がよくない本当の理由を医療視点で解説
【オンラインで学ぶ運動療法】関節のパフォーマンスを上げる運動指導
正常運動と異常運動を「体感」して、明日から“説明して介入できる”PTへ こちらはオンラインセミナーのご案内になります。 対象は、 理学療法士・作業療法士 運動療法に携わる方 初心者大歓迎 こんな方にお…
運動と睡眠は切り離せない。 機能改善の鍵は“関係性”にあった。PT/OT向けセミナー
こちらの記事は ・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 対象となるオンラインセミナーのご案内です。 ●こんな悩みありませんか? ☑寝不足でパフォーマンスが安定しないクライアントがいる☑運動指導しても…
寝不足で育つ子の見えない格差|睡眠時間が足りないと何が起きる?子どもの未来に生まれる“静かな分岐点”
【リハ職向け】予防視点のリハ睡眠──施術効果が続く身体づくりのためにできること──
🔍こんな悩み、ありませんか? ☑ 施術・トレーニング後は良いのに、すぐ元に戻る人がいる☑ 可動域や動作の改善が、翌日には低下してしまうことがある☑睡眠ってそもそもどう評価していいかわからない☑ 睡眠の…
ノンレム睡眠からステージ4が消えた理由|深睡眠は減った?分類変更を科学的に解説

よくある質問(FAQ)
Q:不合理な脳に対して、どんな改善法が一番効きますか?
“脳の不合理さ”に打ち勝つのではなく、“不合理な脳前提”で仕組みを整えることが重要です。
人間は合理よりも感情や環境に左右される生き物!
だからこそ以下の3つの「無意識設計」が有効です。
- 習慣のトリガーを固定する:歯磨き→読書→就寝、のように順番で行動を自動化。
- 環境のナッジ:照明を暗くし、スマホはベッドに持ち込まず、「眠る環境に体が吸い込まれる」仕掛けを。
- 感情報酬を使う:翌朝の気分・肌ツヤ・集中力など“ポジティブな実感”を言語化して記録。感情脳(扁桃体)にごほうびを与えるように。
脳科学・行動経済学・作業療法の三位一体で、「やる気に頼らず眠れる仕組み化」が王道です。
Q:リベンジ夜ふかしをやめたいけど難しいです…
「自分を取り戻す時間が夜しかない」人ほど、夜ふかしは“無意識の抵抗行動”になっています。
これは単なる睡眠習慣の問題ではなく、日中の満たされなさ・自由度の低さが背景にあります。
対策としては以下の3点がオススメです
- 日中に「快」のタスクを意識的に入れる:お気に入りの飲み物、ちょっとした散歩、好きな人との雑談など、小さな満足の積み重ねが「夜の反動」を減らします。
- 昼休みを“自分へのご褒美時間”に設計する:仕事に追われた日こそ、「昼に自分を満たす」ことで夜の自分時間が“不要”になることも。
- 「やりたくないことを後に回す=寝たくない」に変換されることも多いため、寝る前のネガティブ作業(明日の準備・メール返信など)は避けてOKです。
“夜ふかし”は行動でなく「心の叫び」である——そう理解することから、改善の第一歩が始まります。
「どういう生き方したいか」そんなところに繋がると思っています。
Q:何から始めればいいかわかりません。
スタートラインに立つときは、「目標」ではなく「導線」を変えるのがコツです。
意志ややる気に頼らず、環境を変えるだけで自然に睡眠の質が上がる方法があります。
おすすめは以下のステップ!
- 照明の見直し(光の質と量)
→ 夜は暖色系の間接照明に。メラトニンの分泌をサポートします(Harvard Health Publishing, 2015)。 - “寝床以外で眠気を作る”習慣
→ ストレッチ・読書・アロマ・音楽など、身体を静かに落ち着ける「儀式」を1つ加えると、眠気が自然に高まります。自分にとって「気持ちいいと感じれる」がポイント! - “朝起きた自分に感謝される夜”を選ぶ
→ 日記アプリやToDoリストで、前日の快眠とその後の集中・気分の変化を可視化。習慣は「続けた自分を好きになること」で継続します。
まずは“眠る前1時間”に焦点を当て、全体ではなく「夜の導線」に絞るとスタートしやすいです。

\書籍はWEBで購入可/

\睡眠オタのYouTubeチャンネル/

\どんな活動してるの?/


\書籍はWEBで購入可/

\睡眠オタのYouTubeチャンネル/

\どんな活動してるの?/

参考文献
- Killgore, W. D. S. (2010). “Effects of sleep deprivation on cognition”
- Pilcher, J. J., & Huffcutt, A. I. (1996). “Effects of sleep deprivation on performance: A meta-analysis”
- Van Dongen, H. P. A. et al. (2003). “The cumulative cost of additional wakefulness”
- Kroese, F. M. et al. (2014). “Bedtime procrastination: Introducing a new area of procrastination”
- Zimbardo, P. G., & Boyd, J. N. (1999). “Time Perspective Theory”