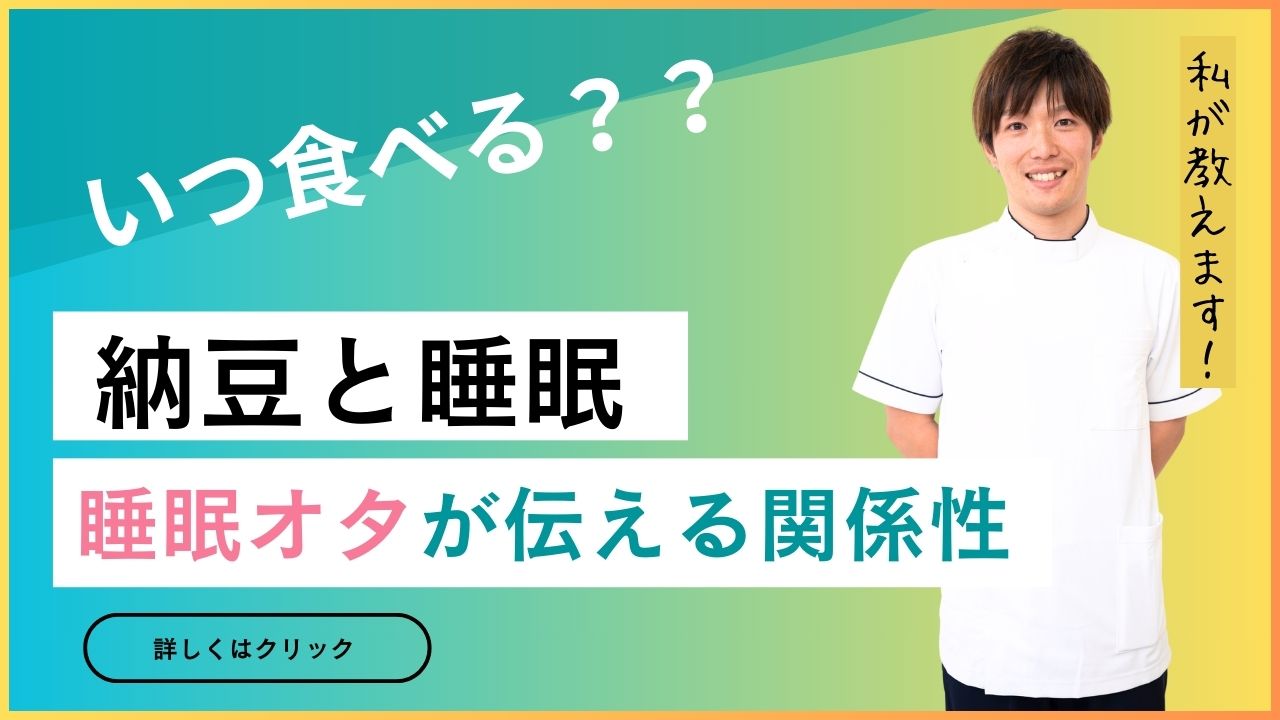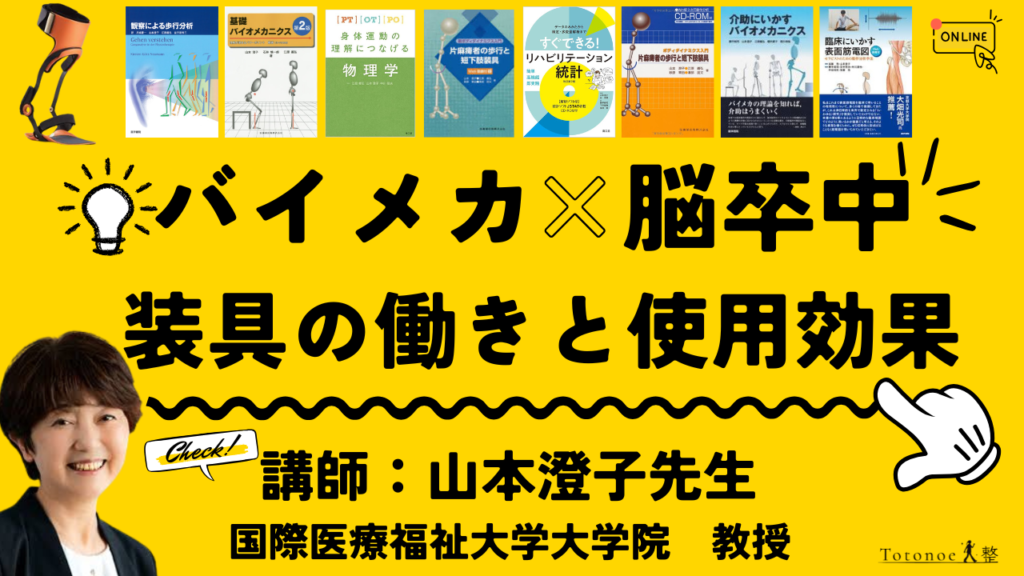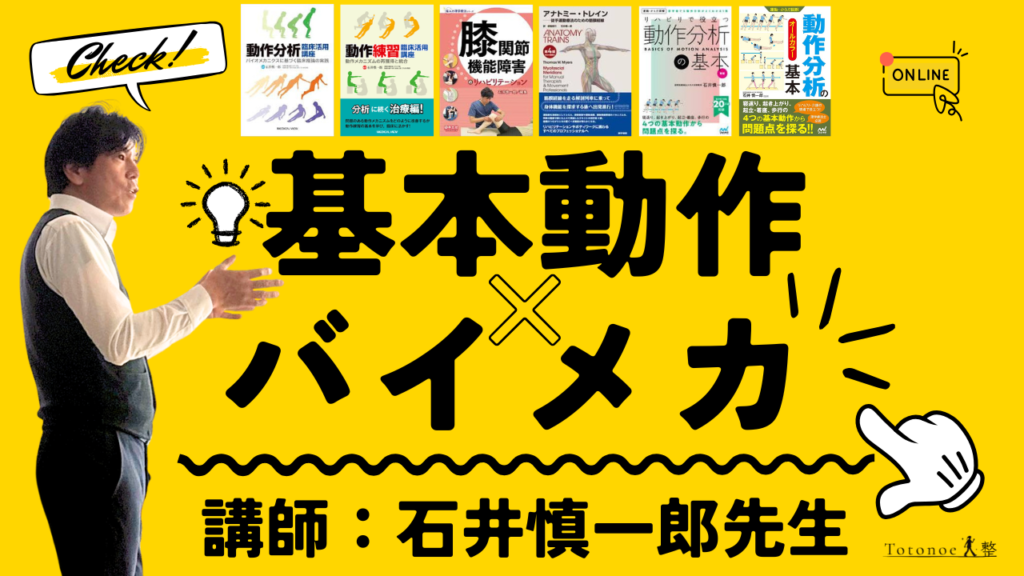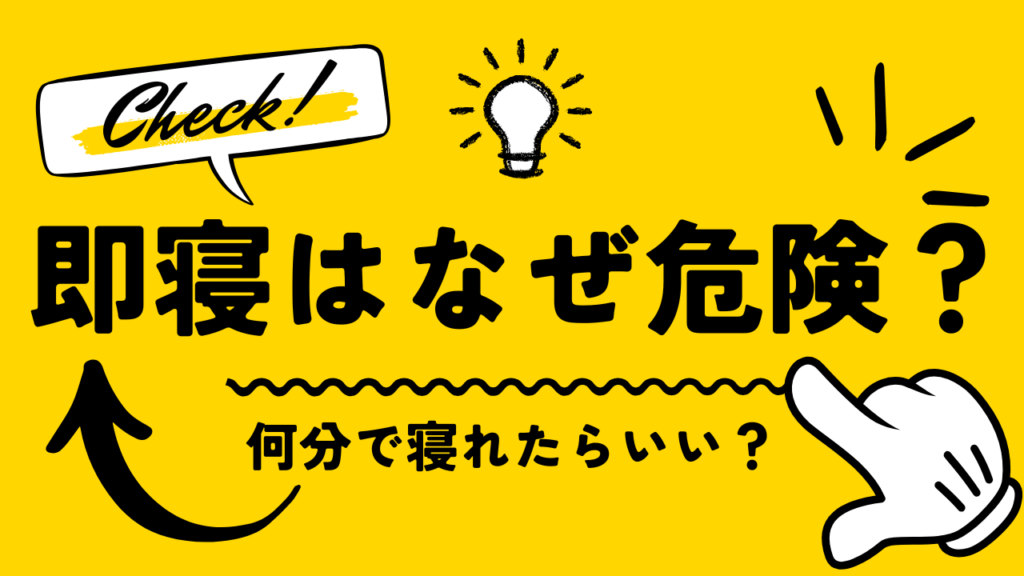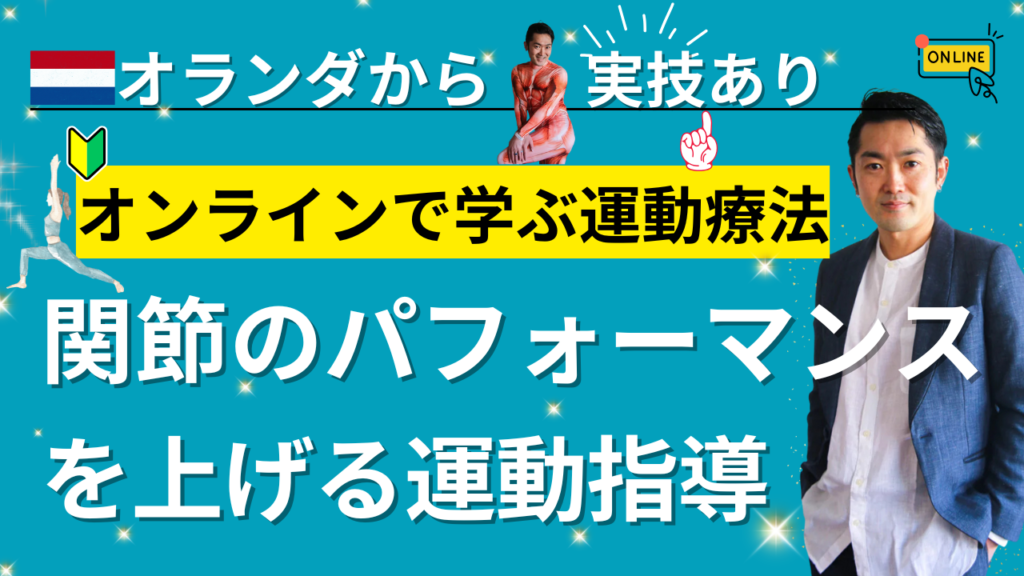皆さん納豆は好きですか?私は大好きです!
さて、納豆が睡眠にどのような影響を与えるか、ご存知でしょうか?
この記事では、納豆と睡眠の関係について詳しく解説し、科学的な視点からその効果を探ります。

目次
納豆と栄養成分
納豆とは?
納豆は、日本の伝統的な発酵食品で、大豆を納豆菌(Bacillus subtilis)で発酵させたものです。
その特有の粘りと匂いが特徴で、多くの栄養素が含まれています。
納豆の栄養成分
- タンパク質:大豆由来の良質なタンパク質が豊富
- ビタミンK2:骨の健康に重要
- ビタミンB群:エネルギー代謝に不可欠
- イソフラボン:抗酸化作用を持つ
- ナットウキナーゼ:血栓を溶解する酵素

睡眠の基本メカニズム
睡眠は脳と体の回復に不可欠で、以下の二つのメカニズムによって調節されます。
1. サーカディアンリズム(概日リズム)
体内時計とも呼ばれ、24時間周期で体の機能を調節します。
メラトニン(天然の睡眠薬といわれるホルモン)というホルモンが深く関与し、夜になると分泌が増加します。
2. ホメオスタティックスリープドライブ
覚醒時間に応じて睡眠欲求が高まるメカニズムです。長時間覚醒していると睡眠圧が高まり、睡眠欲求が強くなります。
▼サーカディアンリズムについて▼
納豆の栄養成分とその効果
納豆に含まれる栄養成分は、睡眠に直接的および間接的な影響を与えることが知られています。
ビタミンB群とメラトニンの生成
ビタミンB6は、セロトニンとメラトニンの生成に必要不可欠です。
納豆に含まれるビタミンB群は、これらのホルモンの合成を助け、質の高い睡眠をサポートします。
トリプトファンとセロトニン
納豆にはトリプトファンというアミノ酸が含まれています。
トリプトファンは、脳内でセロトニンに変換され、セロトニンはメラトニンに変わります。このプロセスは、睡眠の質を向上させる鍵となります。
ナットウキナーゼと血流改善
ナットウキナーゼは血栓を溶解する作用があり、血流を改善します。良好な血流は、脳の酸素供給を促進し、質の高い睡眠をサポートします。

納豆と睡眠の関係
納豆の摂取と睡眠の質
複数の研究によると、納豆の摂取は睡眠の質にポジティブな影響を与えることが示されています。納豆に含まれるトリプトファンとビタミンB群が、メラトニンとセロトニンの生成を促進し、リラックス効果をもたらします。
科学的根拠
ある研究では、納豆を定期的に摂取することで、睡眠の深さと持続時間が改善されることが確認されています。
また、夜間の覚醒回数が減少し、全体的な睡眠の質が向上することが報告されています。
▼ホルモンと睡眠の質について▼
納豆を摂取するタイミングと方法
適切なタイミング
睡眠の質を向上させるためには、朝食時に納豆を摂取するのが効果的です。
トリプトファンがセロトニンに変わり、夜間にメラトニンが分泌されるまでの時間を考慮すると、朝に摂取することが最適です。
摂取方法
納豆はそのまま食べるだけでなく、以下のようなアレンジも可能です。
- 納豆ご飯
- 納豆サラダ
- 納豆パスタ
- 納豆オムレツ
これらのレシピを活用して、日常的に納豆を摂取することができます。

医学的見解と最新研究
最新研究
最近の研究では、納豆に含まれる成分がどのように睡眠に影響を与えるかがさらに詳しく解明されています。
特に、納豆の発酵過程で生成されるペプチドが、リラックス効果をもたらすことが注目されています。
Lee, J., et al. (2019). “The effects of fermented soybean products on sleep quality in adults: A randomized, double-blind, placebo-controlled study.” Journal of Functional Foods, 57, 215-220.
医学的見解
医療専門家の間でも、納豆の摂取が健康な睡眠をサポートすることは広く認められています。
特に、納豆の栄養成分がストレスの軽減や血流の改善に寄与することが、多くの研究で示されています。
納豆の摂取が血圧や酸化還元バランスに与える影響を評価し、血流改善やストレス軽減に寄与する可能性があります。

\ 最新の記事をスワイプ👆⇒ /
【寝ると片足が開くのはなぜ?】仰向けで足が外に倒れる原因と骨盤への影響を作業療法士が解説
なぜ睡眠薬を飲み続けても不眠は治らないのか?|効かない本当の理由を作業療法士が解説
保護中: 山本澄子先生セミナー受講生専用 ※3/31まで
保護中: 石井慎一郎先生セミナー受講生専用 ※3/31まで
布団に入ってすぐ寝る人は要注意?「即寝」がよくない本当の理由を医療視点で解説
【オンラインで学ぶ運動療法】関節のパフォーマンスを上げる運動指導
正常運動と異常運動を「体感」して、明日から“説明して介入できる”PTへ こちらはオンラインセミナーのご案内になります。 対象は、 理学療法士・作業療法士 運動療法に携わる方 初心者大歓迎 こんな方にお…

実践編:納豆を使った健康睡眠法
日常生活での取り入れ方
日常生活に納豆を取り入れるための簡単な方法を以下に紹介します。
- 朝食に納豆:トーストやヨーグルトと一緒に
- 昼食に納豆サラダ:野菜と一緒に栄養バランスを
- 夕食に納豆ご飯:シンプルで美味しい
おすすめレシピ
- 納豆オムレツ:納豆と卵を混ぜてフライパンで焼くだけ
- 納豆パスタ:パスタと納豆を絡めて、醤油で味付け
これらのレシピは簡単に作ることができ、忙しい生活の中でも無理なく納豆を取り入れることができます。

注意点
- アレルギー:大豆アレルギーがある場合は納豆の摂取を避けましょう。
- 過剰摂取:納豆の過剰摂取は、逆に消化不良を引き起こすことがあります。適量を守りましょう。
💡“夜納豆”で睡眠の質を高めよう!
リラックス成分と成長ホルモン促進で「自然な眠り」をサポート
血行・代謝・抗酸化の3方向から健康にもアプローチ
ご飯の温度・栄養の組み合わせで効果を最大化
夜に納豆を取り入れることで、睡眠・美容・健康の3つを同時にケアできます。忙しい日々でも、夜ご飯の一品に加えるだけで手軽に続けられますよ。
夜納豆の習慣、ぜひ試してみてはいかがでしょうか?運動や睡眠環境と組み合わせることで、さらに快眠効果が高まります。
🥣夜納豆の食べ方の工夫
・温度に注意
熱々のご飯に載せるとナットウキナーゼが減少します。冷ましたご飯や常温での摂取がおすすめです。
・カルシウムと一緒に
チーズやヨーグルトと組み合わせることで、ビタミンK2との相乗効果が期待できます。骨・腸・血管に嬉しい組み合わせです。
・ビタミンCをプラス
鉄の吸収を促すため、トマトや果物と一緒に摂るのが効果的です。
・水分補給を忘れずに
繊維の働きには水分が必要です。白湯やハーブティーと一緒に摂ると消化もスムーズです。
▼気になる記事5選▼
よくある質問
質問1: 納豆を食べるときに一緒に摂取すると効果が高まる食材はありますか?
納豆と一緒にビタミンCが豊富な食材(例えば、ピーマンやブロッコリー)を摂取すると、ビタミンCがトリプトファンの吸収を助け、セロトニン生成を促進します。
また、カルシウムを含む食品(牛乳やヨーグルト)と一緒に摂取することで、ビタミンK2の効果が高まり、骨の健康を維持するのにも役立ちます。
質問2: 納豆が苦手な場合、他に同様の効果が期待できる食品はありますか?
納豆が苦手な場合、同様の発酵食品であるキムチやヨーグルトも、腸内環境を整える効果があります。
また、トリプトファンを多く含む食品としては、チーズやターキー、豆類が挙げられます。これらを摂取することで、セロトニンとメラトニンの生成をサポートし、睡眠の質を向上させることが期待できます。
質問3: 納豆を毎日食べると、過剰摂取になるリスクはありますか?
納豆は非常に健康的な食品ですが、過剰摂取によるリスクも考慮する必要があります。
特にビタミンK2は、血液凝固に関与するため、抗凝固薬を服用している方は注意が必要です。
また、大豆イソフラボンの過剰摂取はホルモンバランスに影響を与える可能性があるため、1日1パック程度を目安にすることが推奨されます。
質問4: 納豆を摂取することで期待される具体的な睡眠改善効果は何ですか?
納豆の摂取により、メラトニンの生成が促進され、睡眠の質が向上することが期待されます。
具体的には、入眠までの時間短縮、夜間覚醒の減少、深いノンレム睡眠の増加が報告されています。
これらの効果は、納豆に含まれるトリプトファンとビタミンB群が、脳内でのセロトニン生成を促進することに起因します。
質問5: 納豆が睡眠に及ぼす効果を最大限に引き出すためには、どのくらいの期間継続して摂取する必要がありますか?
納豆が睡眠に及ぼす効果を最大限に引き出すためには、少なくとも数週間から数ヶ月の継続摂取が推奨されます。
これは、体内での栄養素の蓄積や腸内フローラの改善が徐々に進行するためです。
長期的に安定した効果を得るためには、日常的な摂取を心がけることが重要です。
引用文献
- Sumi, H., et al. “A novel fibrinolytic enzyme (nattokinase) in the vegetable cheese natto; a typical and popular soybean food in the Japanese diet.” Experientia 45.10 (1989): 1031-1033.
- Yamori, Y., et al. “Dietary Prevention of Cardiovascular Diseases: Lessons from Mediterranean and Japanese Diets.” World Review of Nutrition and Dietetics. Vol. 109. Karger Publishers, 2014. 1-10.
- Hidaka, M., et al. “Effect of Natto Diet on Blood Pressure and Redox Balance of Individuals with High-Normal Blood Pressure or Grade I Hypertension.” Hypertension Research 40.6 (2017): 579-584.
- Lee, J., et al. “The effects of fermented soybean products on sleep quality in adults: A randomized, double-blind, placebo-controlled study.” Journal of Functional Foods 57 (2019): 215-220.
- Kuriyama, S., et al. “Green tea consumption and cognitive function: a cross-sectional study from the Tsurugaya Project.” The American Journal of Clinical Nutrition 83.2 (2006): 355-361.
- 健康づくりのための睡眠ガイド2023