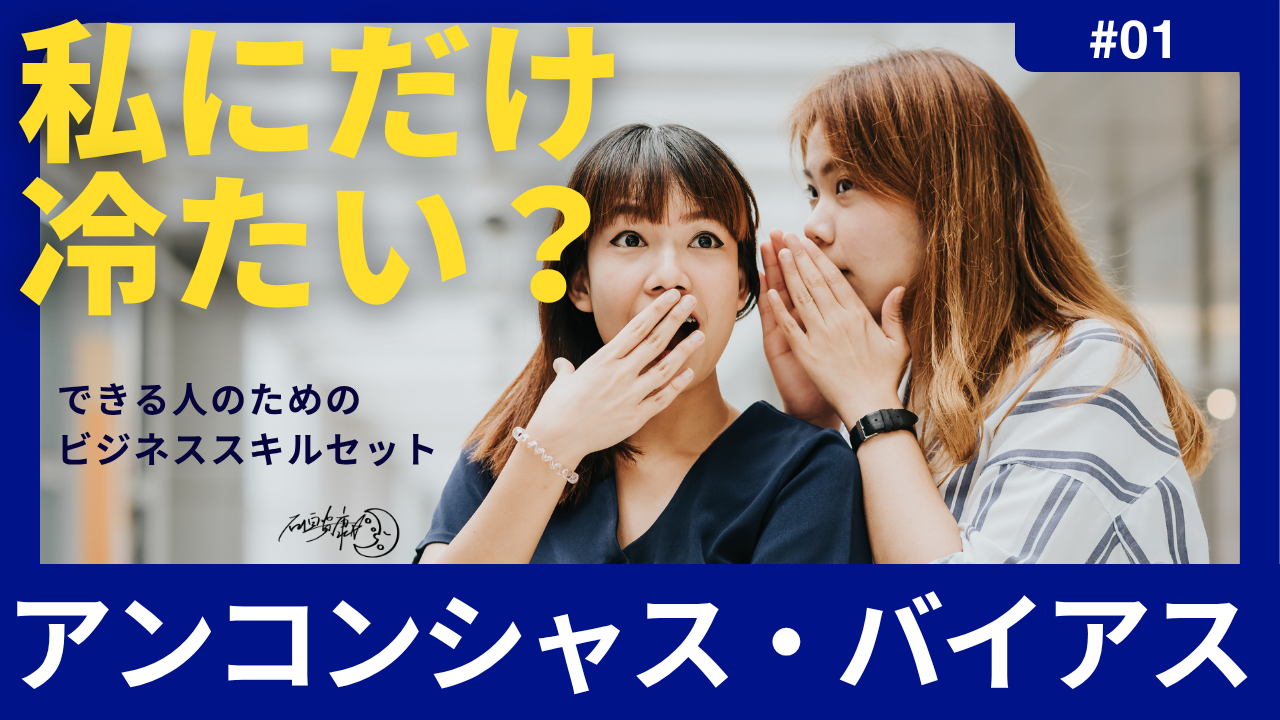\この記事を書いた人/
作業療法士・睡眠専門家としての医療的専門性に加え、企業の経営企画や人材育成支援に実務レベルで関わる「人的資本経営の伴走者」、石垣貴康が執筆しています。
これまでに、企業への健康投資導入や社内講座提供、ブランディング支援、助成金を活用した人材開発講座の企画・監修などを多数担当。
さらに、睡眠と健康をテーマにした書籍を出版し、専門家としてメディア出演の実績もあります。
自身も複数の事業を運営しながら、「科学的根拠 × 現場実践」の視点で、“働く人と組織=環境が健康的に成果を出す仕組みづくり”を支援しています。

目次
アンコンシャス・バイアスとは?
言葉の意味と定義
「アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)」とは、私たちが自覚しないまま抱いている思い込みや先入観のことです。
見た目、性別、年齢、職業、肩書きなど、表面的な情報だけで人や状況を判断してしまう“脳の自動処理”といえます。
『ファスト&スロー』(ダニエル・カーネマン著)では、「人間の判断は2つの思考システム──直感的で速い“システム1”と、論理的で遅い“システム2”によって行われる」とされています。バイアスは“システム1”が生み出す直感的処理の副産物なのです。
なぜ人は“無意識の思い込み”を持つのか?
脳は一日に数万件もの情報を処理しています。
その膨大な情報量を効率的に処理するため、「過去の経験」や「社会からの刷り込み」に頼って判断をショートカットしようとするのです。
これがバイアスの正体です。
バイアスの種類と実生活での例
- 性別バイアス:「女性は感情的」「男性はリーダー向き」
- 年齢バイアス:「若いから頼りない」「年配だから経験豊富」
- 外見バイアス:「見た目で仕事ができそう/できなさそう」
- 立場バイアス:「上司は理解してくれない」「新人は何も分からない」
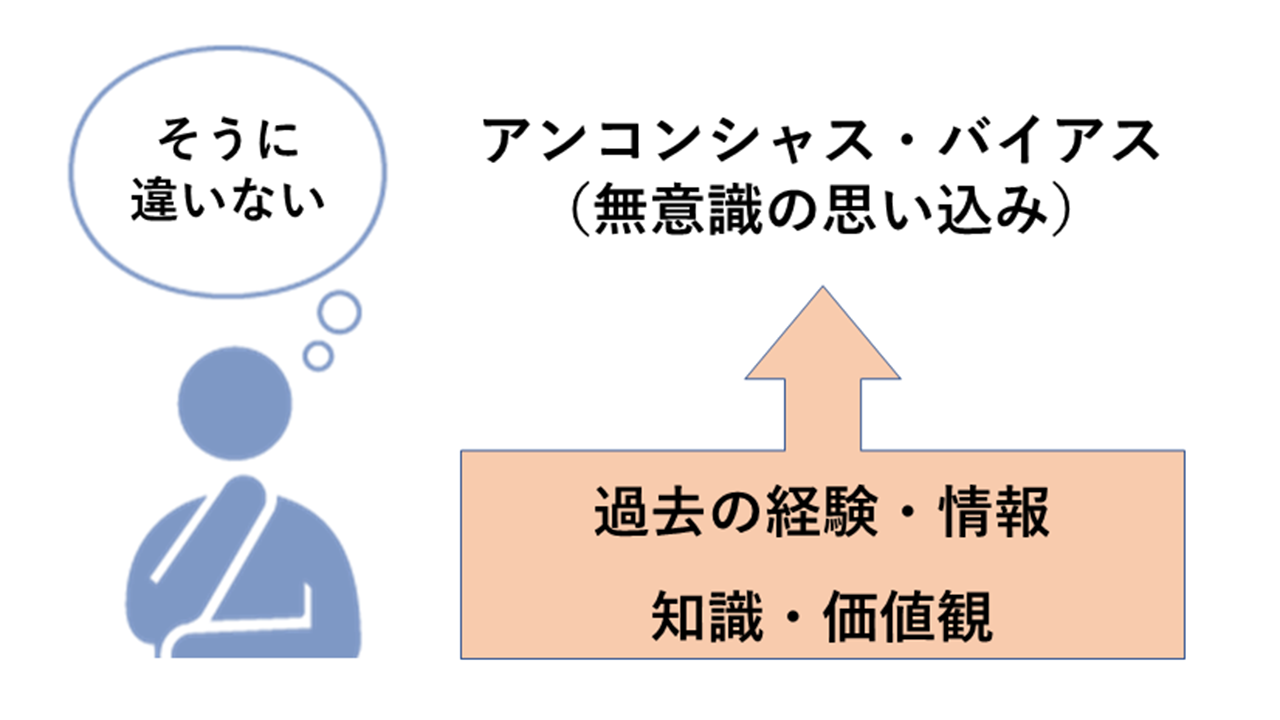
職場でありがち“見えない偏見”の例
「あの人、きっとこういうタイプ」
同じ部署にいても「○○さんは理屈っぽいから無理」と決めつけたり、話す前から“苦手”をつくってしまうこと、ありませんか?
これは立派なアンコンシャス・バイアスです。
「男性なのに感情的だよね」
感情表現は人間らしさの一部ですが、「性別」によって求める態度を無意識に変えているケースもあります。
男性が落ち込んでいたり涙を流すと「弱い」と評価されるのも、バイアスの影響です。
「あの部署は頼りにならない」
過去に一度ミスがあっただけで、部署全体を「仕事ができない集団」として認識してしまうことも。
情報は更新されているのに、自分の中のラベルは貼り替えられていないことがあります。
冷たくされたと感じる“認知のズレ”
「なんで自分にだけあの人は冷たいの?」と感じたとき、相手の態度の背景には“こちらへの苦手意識”ではなく、“過去の誰かと重ねて見ている”という無意識のバイアスが関係していることもあります。
『嫌われる勇気』(岸見一郎著)では、「他者の課題は自分が引き受けるべきものではない」と説いています。相手の反応に過度に左右されるのではなく、「自分がどう解釈するか」に意識を向けることで、冷たさに対する捉え方も変わってきます。

システム1とシステム2|無意識の思考と意識的な判断の違い
アンコンシャス・バイアスを理解する上で欠かせないのが、心理学者ダニエル・カーネマンが提唱した「システム1」と「システム2」という二つの思考モードです。
これを知ることで、なぜ私たちが偏った判断をしてしまうのかがクリアになります。
システム1|瞬時の判断を下す「自動運転モード」
- 特徴:感情や直感をベースに、瞬間的に反応する思考
- メリット:経験則からすばやく意思決定できる
- デメリット:情報を精査せず、先入観や思い込みに左右されやすい
- 職場での例:初対面の相手を「話しやすそう/話しにくそう」と即判断してしまう
システム2|熟考し、論理的に判断する「マニュアル運転モード」
- 特徴:時間をかけて、意識的に考えながら答えを導く
- メリット:複雑な問題を冷静に分析できる
- デメリット:時間と労力がかかるため、常に使うのは困難
- 職場での例:会議で多角的にデータを比較して方針を決める
アンコンシャス・バイアスとの関係
私たちは日常の90%以上をシステム1で判断しています。この「自動運転モード」に潜むのがアンコンシャス・バイアスです。
しかし、偏りに気づいた瞬間にシステム2へ切り替えることで、誤解や不公平な判断を減らせます。
実践ポイント
- 違和感を覚えたら立ち止まる
「なぜそう思ったのか?」と自問する習慣を持つ - データや事実を確認する
感覚ではなく根拠で判断する - 多様な意見を取り入れる
他者の視点はシステム2の思考を促すトリガーになる
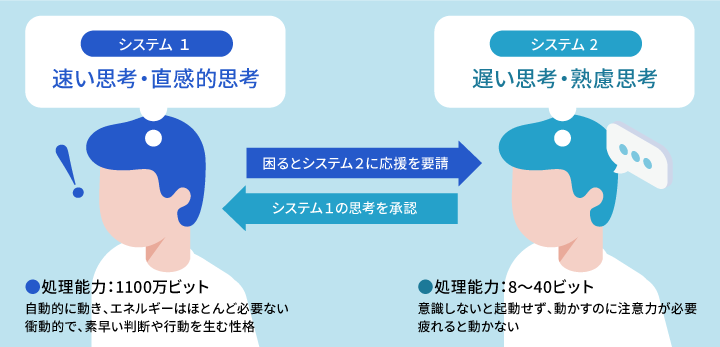
アンコンシャス・バイアスの影響
評価やフィードバックの歪み
上司が「なんとなく合わない」という感覚だけで、特定の部下を過小評価してしまうことがあります。
その背景には無意識の価値観や先入観が潜んでおり、適正な人事評価の妨げになります。
チームの分断・信頼関係の低下
「○○さんはこういう人だから」とラベルを貼ることで、本来の力を発揮できなくなるだけでなく、チーム内の心理的安全性も損なわれます。
メンバー同士が自由に意見を言えない環境は、生産性にも直結します。
無自覚ハラスメントの温床になることも
悪気がなくても、「決めつけ」や「排除的な言動」はハラスメントの原因になります。
「女性なのに強いね」「外国人っぽい顔だね」といった軽口も、相手を傷つけてしまう可能性があるのです。
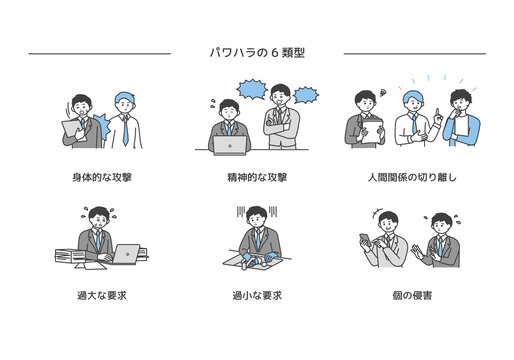
あなたも偏ってる?セルフチェックリスト
10の質問で分かる「思い込み傾向」
- 初対面の人を見た目で判断することがある
- 相手の肩書きによって態度が変わる
- 年齢や性別で相手の能力を想像してしまう
- 「どうせ○○だろう」と決めつけてしまう
- 他人の行動を“性格”で片付けがち
- 「なんか好きになれない」と感じる人がいる
- 自分と違う価値観を否定したくなる
- 相手の背景を深く知ろうとしない
- 過去の経験を元にレッテルを貼る
- 「普通はこうするよね」が口癖になっている
3つ以上当てはまる方は、無意識の思い込みに注意が必要です。
アンコンシャス・バイアスとの向き合い方
① 自分のフィルターに気づく(メタ認知)
まずは「自分がどんな見方をしているか」に気づくことが第一歩です。
気に入らない相手がいる場合、「なぜそう感じるのか?」と問い直すだけでも、バイアスに向き合う視点が養われます。
② 感情と事実を切り分ける習慣
「冷たくされた=嫌われている」とは限りません。相手が忙しかっただけかもしれませんし、ただ無表情なだけかもしれません。
事実と感情を分けて捉える力が、誤解やトラブルを減らします。
③ 多様な視点にふれる(読書・対話)
自分の“常識”は、あくまで一つの見方に過ぎません。異なる立場の人との対話、ノンフィクションや異文化に関する本を読むことで、視野が広がり、バイアスに気づくセンサーが鍛えられます。
『Think Again』(アダム・グラント著)では、「思い込みを手放し、柔軟に考え直すことこそが、現代に求められる知性だ」と語られています。バイアスに気づき、アップデートすることは、まさに“思考の柔軟性”の実践なのです。

職場で実践できる“思い込み”の手放し方
雑談・フィードバックで視野を広げる
仕事の話以外にも雑談やプライベートの一面を知ることで、「この人って意外と◯◯な一面があるんだ」と印象が更新されます。
フィードバックの場でも、「私がどう見えているか」を聞いてみると、バイアスの確認に役立ちます。
観察→質問→共感の3ステップ対話
「なんか違和感あるな…」と思ったら、まず観察。次に問いかけ、相手の背景や理由を聞いてみる。
共感できるポイントを見つければ、バイアスが“理解”に変わる瞬間が生まれます。
「無意識のままにしない」組織の工夫
Googleなどの企業では、アンコンシャス・バイアスに気づく研修を義務化しています。
組織としての取り組みがあることで、個人だけでなくチーム全体で“思い込み”に敏感な文化を育てていけるのです。

まとめ|アンコンシャス・バイアスは「悪」ではない。“認識”から変わる人間関係
- 誰にでもバイアスはある。それを“認めること”が第一歩
- 「正しさ」で裁かず、「背景」を想像する
- 気づくことは、関係性の再構築につながる
アンコンシャス・バイアスは「敵」ではなく、私たちの脳の働きそのもの。
だからこそ、気づき、対話し、少しずつ手放していくことが、人間関係を豊かにする鍵となるのです。
▼気になる記事3選▼

\書籍はWEBで購入可/

\睡眠オタのYouTubeチャンネル/

\どんな活動してるの?/