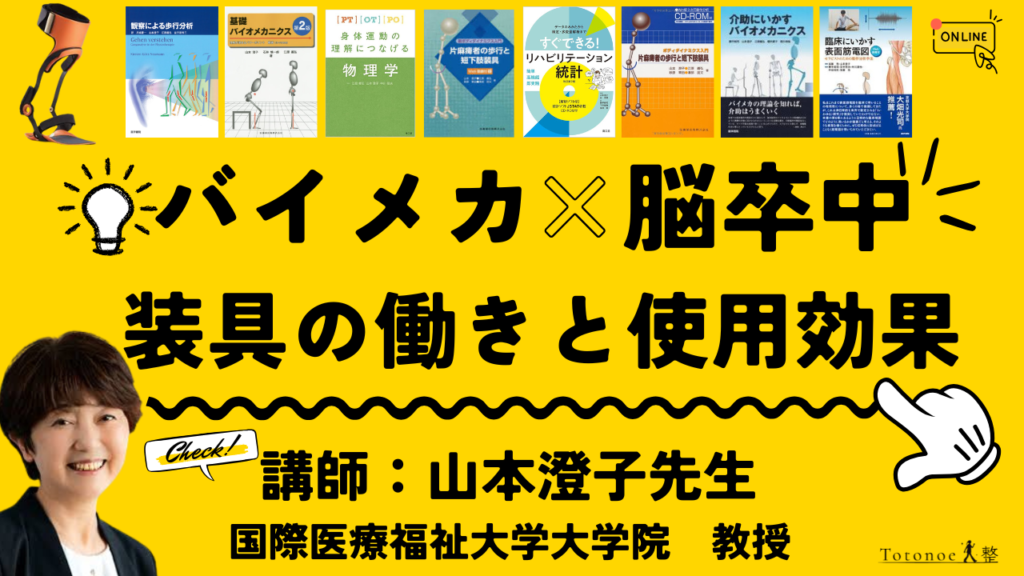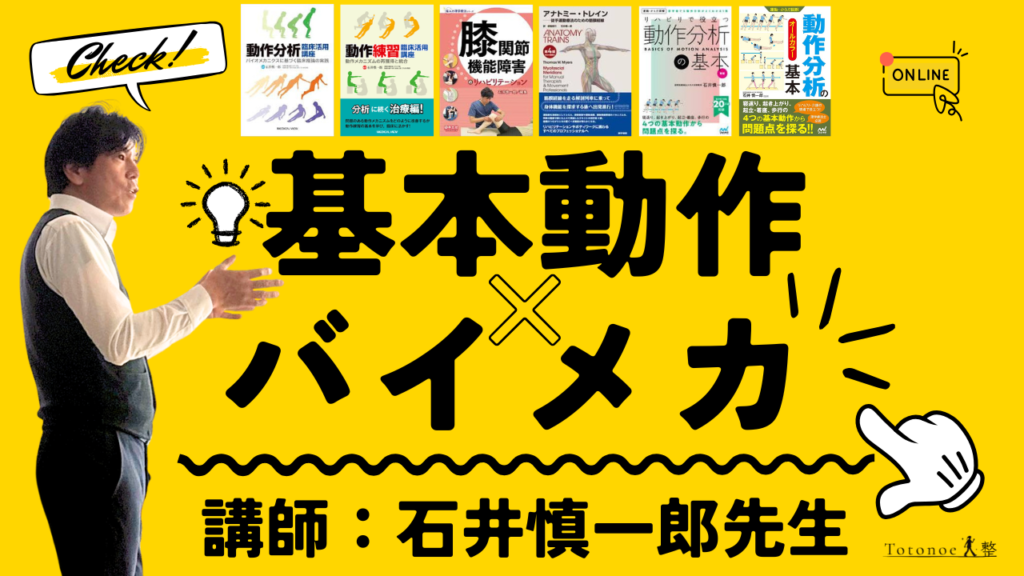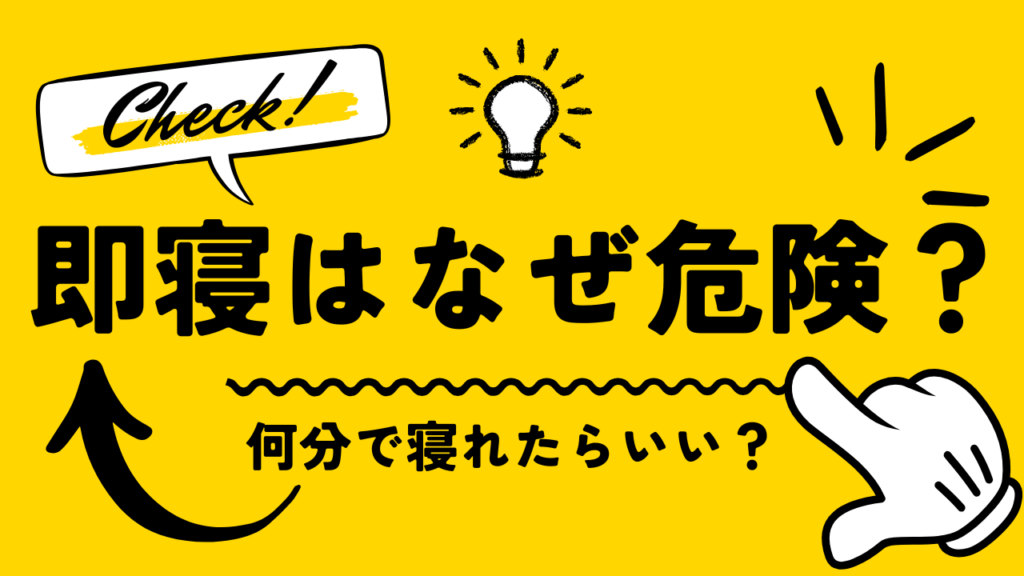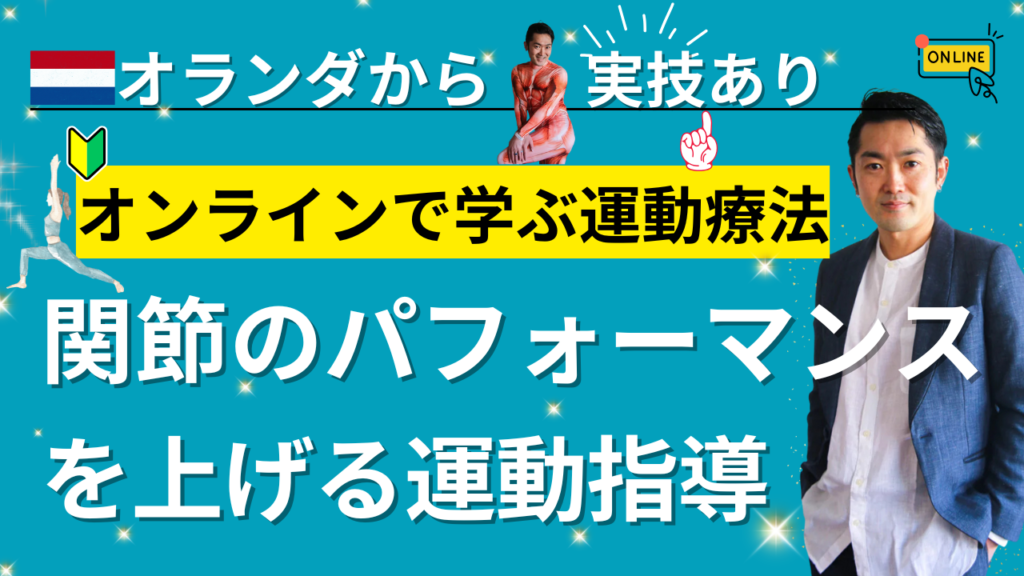はじめに
カレーは多くの人に愛される食べ物ですが、その成分や摂取タイミングが睡眠にどのような影響を及ぼすのかについて知ると面白いです。
案外読んでいただいているこの記事ですが、私がカレーが昔は食べられなかったのですが、カレーが今では大好きで今回の記事を掲載させていただきました。
ここでは、カレーと睡眠の関係について、エビデンスに基づいた情報を提供します。
ぜひ最後までチェックしてくださいね!

目次
1. カレーの成分と睡眠への影響
香辛料(スパイス)
- ターメリック(ウコン):カレーの主要成分であるターメリックには、抗炎症作用があるクルクミンが含まれています。いくつかの研究では、クルクミンがストレス軽減や炎症の抑制を通じて、睡眠の質を向上させる可能性が示唆されています。
- カプサイシン:辛味をもたらすカプサイシンは、体温を上昇させ、新陳代謝を促進します。これにより、一時的に睡眠を妨げることがありますが、体温の低下と共に眠気を誘発することもあります。
トリプトファン
カレーには、鶏肉や豆類といったトリプトファンを豊富に含む食材が使われることが多いです。
トリプトファンは、セロトニンおよびメラトニンの前駆体であり、これらは睡眠の調節に重要な役割を果たします。
2. 消化と睡眠
カレーは一般的に消化が重い食品とされています。脂肪分やスパイスが多く含まれるため、消化に時間がかかることがあります。
特に寝る前にカレーを摂取すると、消化不良を引き起こし、睡眠の質を低下させる可能性があります。

3. 睡眠リズムと食事のタイミング
睡眠前の食事は慎重に考える必要があります。
就寝前は重い食事を避け、軽めの食事を心がけることで、睡眠への悪影響を最小限に抑えることができます。
例えば、ココナッツミルクやヨーグルトを使った軽めのカレーを選ぶと良いでしょう。
▼食後の眠気ランキング(Youtube Live)▼
4. 個人差
食物が睡眠に与える影響には個人差があります。
ある方にとってはカレーがリラックス効果をもたらすかもしれませんが、他の人にとっては逆に刺激になりうることもあります。

おすすめのカレーの食べ方
- 軽いカレーを選ぶ:ココナッツミルクやヨーグルトを使用したカレーは消化が良く、睡眠への影響も少ないです。
- 食事のタイミングを調整する:就寝の2〜3時間前までに食事を終えるようアドバイスしましょう。これにより、消化の影響を最小限に抑えることができます。
- 個人の好みを観察する:人それぞれの反応を観察し、最適な食事のタイミングや内容を見つけるよう助言しましょう。

\ 最新の記事をスワイプ👆⇒ /
なぜ睡眠薬を飲み続けても不眠は治らないのか?|効かない本当の理由を作業療法士が解説
保護中: 山本澄子先生セミナー受講生専用 ※3/31まで
保護中: 石井慎一郎先生セミナー受講生専用 ※3/31まで
布団に入ってすぐ寝る人は要注意?「即寝」がよくない本当の理由を医療視点で解説
【オンラインで学ぶ運動療法】関節のパフォーマンスを上げる運動指導
正常運動と異常運動を「体感」して、明日から“説明して介入できる”PTへ こちらはオンラインセミナーのご案内になります。 対象は、 理学療法士・作業療法士 運動療法に携わる方 初心者大歓迎 こんな方にお…
運動と睡眠は切り離せない。 機能改善の鍵は“関係性”にあった。PT/OT向けセミナー
こちらの記事は ・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 対象となるオンラインセミナーのご案内です。 ●こんな悩みありませんか? ☑寝不足でパフォーマンスが安定しないクライアントがいる☑運動指導しても…

結論
カレーが睡眠に与える影響は、その成分や摂取タイミングに大きく依存します。
カレーを楽しみながらも、良質な睡眠を得るための適切なアプローチを見つける手助けをしましょう。
▼睡眠オタOTオススメ記事7選▼
よくある質問と回答
質問1: カレーに含まれるターメリックのクルクミンは、具体的にどのように睡眠に影響を与えるのですか?
クルクミンは抗炎症作用を有しており、体内の炎症マーカーを低減させることで、中枢神経系の機能を安定させます。
これにより、ストレス応答の軽減や神経伝達物質のバランス調整が促進され、結果的に睡眠の質が向上することが報告されています。
また、クルクミンは抗酸化作用も持ち、酸化ストレスの軽減を通じて睡眠障害のリスクを低減させる可能性があります。
質問2: カレーの摂取が直接的に睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌に影響を与えることはありますか?
カレー自体が直接的にメラトニンの分泌を促進するわけではありませんが、カレーに含まれるトリプトファンが間接的に関与します。
トリプトファンはセロトニンの前駆体であり、セロトニンはメラトニンの前駆体です。
したがって、トリプトファンを多く含む食品を摂取することで、結果的にメラトニンの合成が促進される可能性があります。
質問3: 辛いカレーを食べると、体温が上がるのはなぜですか?そしてその影響は睡眠にどう関係するのですか?
辛味成分であるカプサイシンは、体内の熱産生を促進する作用があります。
これにより、一時的に体温が上昇します。体温の上昇は覚醒状態を促進するため、一時的に入眠を妨げることがあります。
しかし、体温がその後低下する過程で、体はリラックスしやすくなり、結果的に深い睡眠が促進されることもあります。
これは体温の自然な日内リズムに従った反応です。
質問4: 寝る前にカレーを食べると、胃酸逆流や消化不良のリスクが高まると聞きましたが、本当ですか?
寝る前にカレーを食べると、胃酸逆流や消化不良のリスクが高まる可能性があります。
カレーには脂肪分やスパイスが多く含まれており、これらは胃酸の分泌を促進し、胃内容物の逆流を引き起こしやすくします。
特に、仰向けで寝ると逆流が起きやすく、これが睡眠中の不快感や中途覚醒の原因となることがあります。
したがって、カレーは就寝の2〜3時間前に摂取を終えるのが望ましいです。
質問5: カレーを食べることで睡眠の質を向上させるためには、具体的にどのようなカレーを選ぶと良いですか?
睡眠の質を向上させるためには、以下の点を考慮したカレーを選ぶと良いでしょう
- 低脂肪:脂肪分の少ないカレーを選び、消化を助ける。
- 適度なスパイス:胃腸に優しいスパイスを使用し、刺激を抑える。
- タンパク質源:鶏肉や豆類など、トリプトファンを豊富に含む食材を使用する。
- 低糖質:過剰な糖分を避け、血糖値の急激な変動を抑える。
- 自然食材:添加物を避け、新鮮な食材を使用することで、消化器官への負担を軽減する。

\書籍はWEBで購入可/

\睡眠オタのYouTubeチャンネル/

\どんな活動してるの?/