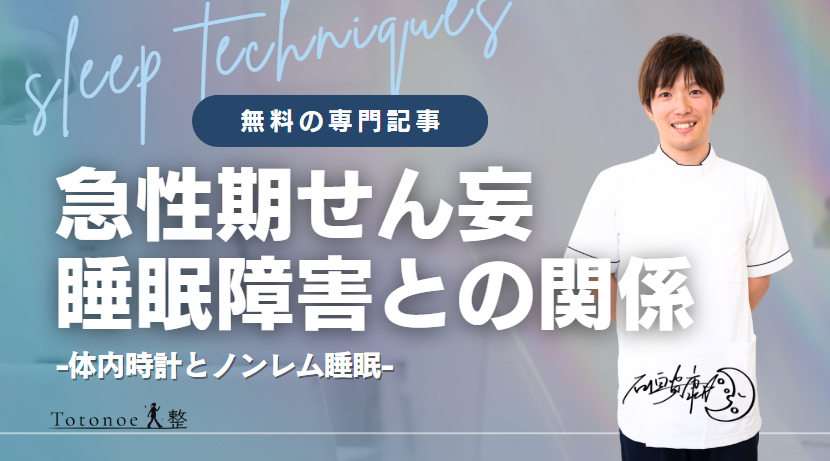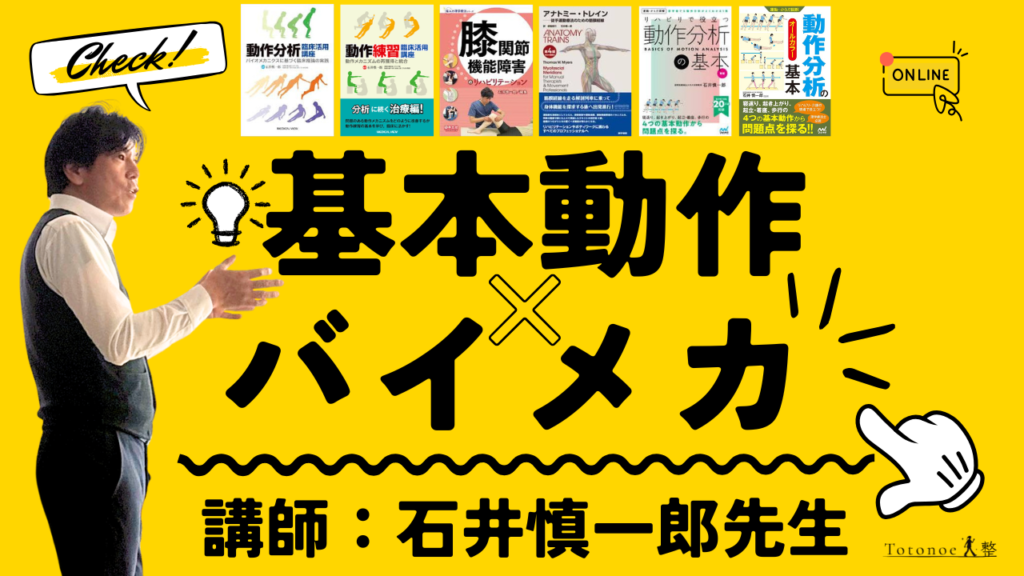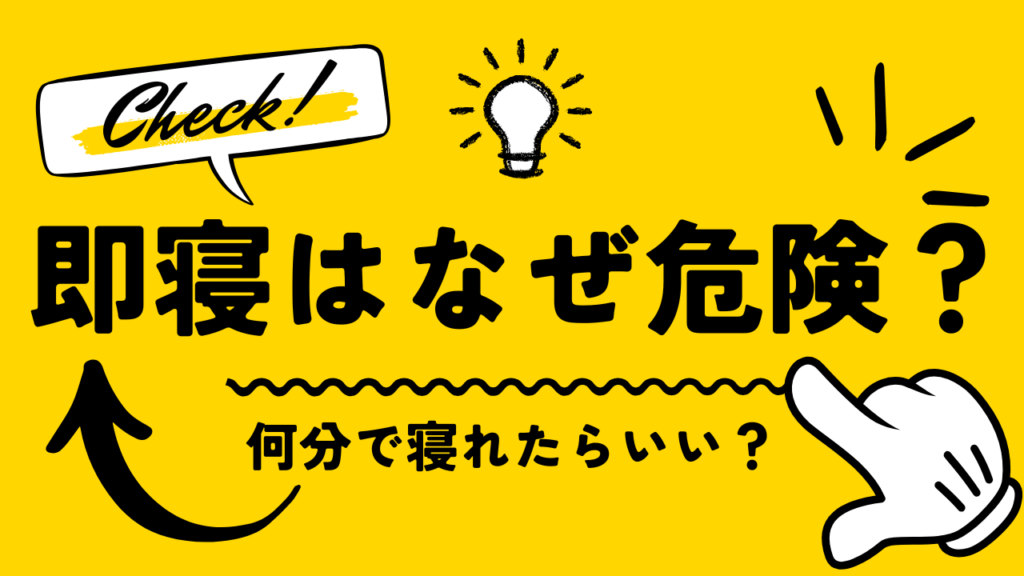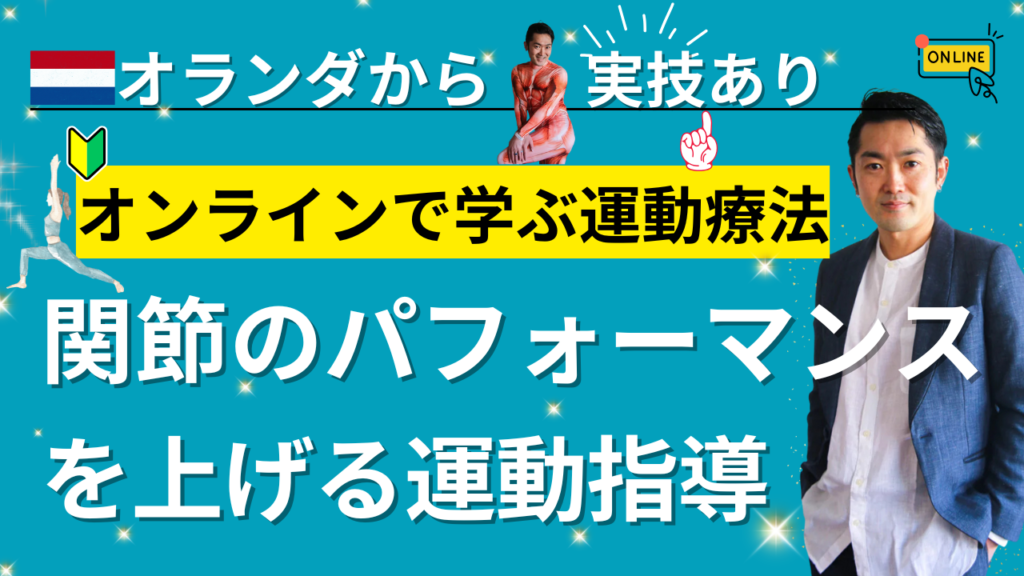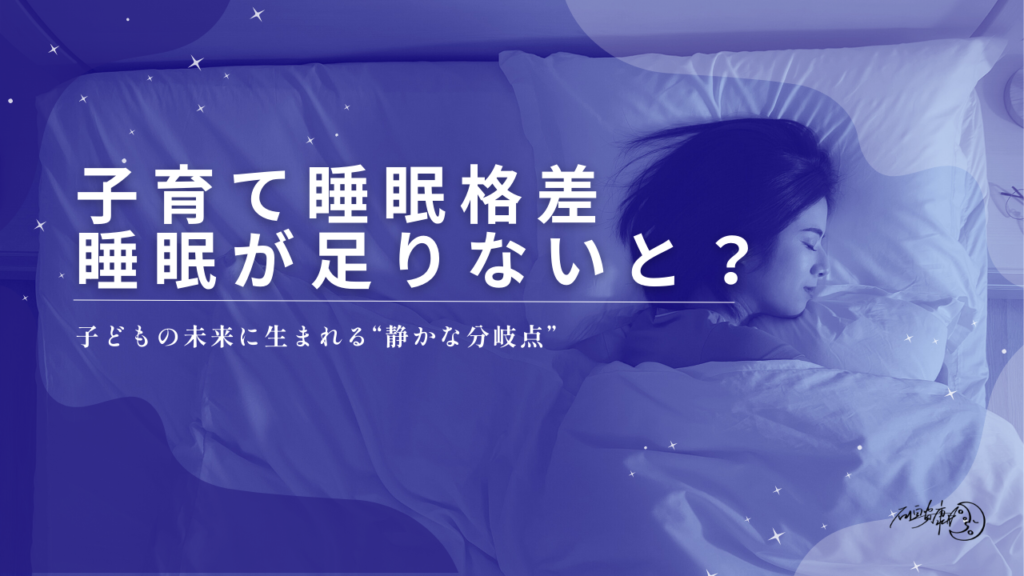目次
はじめに ― 命を守るだけでは足りない“脳のケア”
急性期では、救命処置が最優先。
患者は点滴やモニターに囲まれ、長時間臥床を余儀なくされます。
その結果、睡眠と覚醒のリズムが崩壊し、ノンレム睡眠が断片化。
「脳が休めずに朝を迎える」ことでせん妄のリスクが高まります。
この記事では、体内時計とノンレム睡眠の視点から急性期せん妄を読み解き、現場で実践可能な睡眠介入策をご紹介します。

せん妄とは? ― 急性期に潜む“脳の一過性トラブル”
せん妄(delirium)とは、急激に始まる意識の変容・注意力の低下・認知機能の変動を伴う状態です。
「今どこにいるのかわからない」
「幻覚が見える」
「突然怒り出す」
といった症状が見られます。
医学的には、以下の3つを満たすことが診断基準とされます(DSM-5)。
- 意識水準の変化(ぼんやり、興奮、傾眠)
- 注意障害(集中が続かない、話が噛み合わない)
- 急性発症かつ日内変動
特に急性期病棟では、手術・感染症・薬剤・環境変化などの多重ストレスによりせん妄が起きやすくなります。
中でも「夜になると取り乱す」「昼夜逆転する」といった“夜間せん妄”は、睡眠の質や体内時計の乱れが深く関わっているのです。
![重症患者の管理のイラスト🎨【フリー素材】|看護roo![カンゴルー]](https://img.kango-roo.com/upload/images/ki/siphoning_phenomenon_position_syringe_pump_thumbnail.jpg)
🕰 「ずっと寝ている=体内時計が狂っていく」という悪循環
ヒトの体内時計(サーカディアンリズム)は、光・活動・食事などの刺激によって「今は朝だ」「夜だ」と認識するようにできています。
📉 急性期の睡眠を妨げる要因
🤐 刺激が乏しく、昼と夜の区別がつかない
💡 光環境の乱れ(昼夜区別のない照明)
🌙 断続的な夜間介入(バイタル測定、点滴交換)
🔊 騒音・ナースコール・モニター音
💊 薬剤(ステロイド、抗コリン薬、カフェイン含有薬)
🚷 運動や活動の機会が極端に少ない
🚷 離床制限による日中の活動不足(=夜に眠くならない)
このように、体内時計を“合わせるためのスイッチ”が押されない環境になっているのです。
➡︎ すると、夜になっても脳は“夜”と認識できず、眠気が生じない
➡︎ その結果、夜中に目覚めたり、意味不明な言動(せん妄)が生じることもあります
なぜ急性期でせん妄が起こるのか?
① サーカディアンリズムの崩壊
窓のない病室、24時間点灯、騒音のある環境では、体内時計を調整する光・音・活動といった“時間の手がかり(Zeitgeber)”が欠如します。
その結果、メラトニンの分泌が乱れ、眠気が生じず、夜間覚醒が増えるのです。
② ノンレム睡眠断片化と情報統合障害
ノンレム睡眠、特にステージ3(徐波睡眠)は脳の情報整理や自己認識の再構築に不可欠です。
しかし急性期では、10〜20分おきの処置・アラーム・夜間介入など様々な覚醒要因により睡眠が分断され、脳の“統合力”が落ちてせん妄症状が出やすくなります(Flannery, 2016)。
③ 離床できない→“夜に眠れなくなる”
活動量が低いと、日中に睡眠圧が十分に高まらず、夜になっても自然な眠気が訪れません。
臥床時間は長くても「眠れているわけではない」ため、結果的に睡眠障害 → せん妄へと進行します。
![入院 (不安) [女性患者] のイラスト│看護師イラスト・フリー素材集【無料】│看護師ライフをもっとステキに ナースプラス](https://kango.mynavi.jp/contents/nurseplus/wp-content/uploads/2024/07/186_C_%E8%80%85%E5%A4%A7%E4%BA%BA%E3%83%BB%E5%A5%B3%E6%80%A7%EF%BC%9A%E5%85%A5%E9%99%A2-%E4%B8%8D%E5%AE%89.png)
自己認識と「現実検討力」が不安定になる
ノンレム睡眠中、内側前頭前野(mPFC)や楔前部(precuneus)など、自己意識に関わる領域の活動が一時的に休止します。
このリセットを経ることで、目覚めた時に「私は私」「今ここにいる」という一貫した“自我”が再確立されます。
しかし、断片的なノンレム睡眠では、このプロセスが不完全。
→ その結果、目覚めた後に**「ここはどこ?」「自分が誰か曖昧」「現実と夢の境界が曖昧」**という感覚が残ることがあります。
これも、せん妄の中核的な症状のひとつです。
📌 ノンレム睡眠とは?
ノンレム睡眠(Non-REM sleep)は、主に脳の回復と記憶の整理・自己認識のリセットを担う深い睡眠ステージです。
とくに**ステージ3(徐波睡眠)**では、大脳皮質が広範囲にわたって同期的に脱活動し、脳内の無駄な情報が“整理・選別”されます。
寝ているようで“眠れていない”急性期患者の脳
ICUのポリソムノグラフィ研究では、覚醒と浅いノンレム睡眠の反復が確認され、平均睡眠効率は50%以下という報告もあります(Watson, 2012)。
これは「寝ているように見えても脳は休めていない」状態。
注意力の低下、情緒不安定、錯覚などのせん妄症状が出現しやすくなるのも当然です。

🔄 医療現場での“現実的アプローチ”とは?
✅ 理想論ではなく「現実対応」が必要
「光を当てましょう」「昼夜のリズムを整えましょう」と言っても、そもそも命の危機に瀕している患者にとって、「昼夜の区別」どころではありません。
そこに対して無理に介入するのではなく、“できることから積み上げる”視点が必要です。
急性期でもできる!睡眠ケア5
①朝の高照度光
ポータブル光療法器を使って朝7〜9時に2,500 lxの照射。
自然光がない環境でもメラトニン抑制→覚醒のスイッチが入ります。
朝、昼間に使いましょう。
②日中の刺激を明確に
テレビやラジオは昼のみ使用。
面会は日中に調整し、「昼らしさ」を五感で演出。
まずは環境を調整し、昼夜のメリハリをセッティングしましょう!
③離床できなくても“活動刺激”は作れる
端座位やギャッチアップ。
足底・呼吸・上肢運動による交感神経刺激。
個人的にはギャッチアップできる方は、足底に板を入れて、刺激を入れることをしておりました。
日中に軽く声かけ・会話するだけでもOK。
④夜間は光・音・介入を最小限に
処置・バイタル測定を21時までに集約
夜は300 lx未満の暖色灯+静音
ナースステーションの音漏れ対策も効果的
⑤薬剤の再評価
ベンゾジアゼピン系 → せん妄リスクを上げるため慎重に
メラトニン作動薬(ラメルテオン)は体内時計調整に有用(Al-Aama, 2011)
抗コリン薬やステロイド系薬の影響も要チェック
睡眠ケアを多職種で連携しよう
看護師:介入スケジュールの調整・夜間の照明管理
リハ職:日中の活動提案・体位変換の支援
医師:薬剤調整・ICUプロトコルへの睡眠支援導入
家族:昼の訪室推奨・本人の時間感覚をサポートする声かけ
▼2026年!「お伊勢さん」特別企画!!▼


\ 最新の記事をスワイプ👆⇒ /
保護中: 石井慎一郎先生セミナー受講生専用
布団に入ってすぐ寝る人は要注意?「即寝」がよくない本当の理由を医療視点で解説
【オンラインで学ぶ運動療法】関節のパフォーマンスを上げる運動指導
正常運動と異常運動を「体感」して、明日から“説明して介入できる”PTへ こちらはオンラインセミナーのご案内になります。 対象は、 理学療法士・作業療法士 運動療法に携わる方 初心者大歓迎 こんな方にお…
運動と睡眠は切り離せない。 機能改善の鍵は“関係性”にあった。PT/OT向けセミナー
こちらの記事は ・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 対象となるオンラインセミナーのご案内です。 ●こんな悩みありませんか? ☑寝不足でパフォーマンスが安定しないクライアントがいる☑運動指導しても…
寝不足で育つ子の見えない格差|睡眠時間が足りないと何が起きる?子どもの未来に生まれる“静かな分岐点”
【リハ職向け】予防視点のリハ睡眠──施術効果が続く身体づくりのためにできること──
🔍こんな悩み、ありませんか? ☑ 施術・トレーニング後は良いのに、すぐ元に戻る人がいる☑ 可動域や動作の改善が、翌日には低下してしまうことがある☑睡眠ってそもそもどう評価していいかわからない☑ 睡眠の…

まとめ ― 急性期こそ“眠らせる”より“目覚めさせる”ケアを
急性期におけるせん妄の本質は、睡眠障害と体内時計の乱れにもあります。
長時間の臥床や環境ストレスが、ノンレム睡眠の断片化と概日リズムの崩壊を招きます。
「眠れる環境をつくる」だけでなく、「昼に起きるリズムを整える」ことが、せん妄予防・脳回復・ADL改善への第一歩です。
睡眠オタクな作業療法士として、医療職の皆さまが“脳に優しいケア”を届けられることを願っています。
▼気になる記事5選▼
よくある質問
Q1:急性期では寝かせておくのが一番では?
長時間臥床は“見た目の安静”ですが、脳にとってはむしろ過活動・混乱の要因になり得ます。
急性期の患者では、しばしば「寝ているように見える」=「脳も休んでいる」と誤解されますが、実際には**浅い睡眠と断続的な覚醒の反復(=睡眠の断片化)**が多く、睡眠としての質は非常に低いのが実情です。
このような中途覚醒状態では、大脳皮質の休息や記憶統合、自己認識の再構築が不十分となり、かえって認知の乱れやせん妄を誘発します。
また、臥床による血圧変動や抹消循環の低下は脳血流の安定性を損ねるため、脳機能回復を妨げる側面もあります。
「静かに寝かせておく」ことが必ずしも“脳の休息”ではないという視点が重要です。
Q2:高齢者の睡眠は短くても問題ないのでは?
加齢による生理的変化はありますが、“質の低下”や“昼夜逆転”は病的と考えるべきです。
高齢者では徐波睡眠(ステージ3)の割合が減り、睡眠が浅くなりやすいのは事実です。
しかし、それは「眠らなくてもいい」ではなく、むしろ睡眠の質をどう確保するかが重要になります。
とくに急性期では、
・夜間の覚醒増加
・昼夜の区別がなくなる
・脳の自己再構成機能(プレ睡眠記憶統合・情動調整)が破綻
といった要因により、“睡眠の質的障害”がせん妄を誘発します。
「高齢者だから仕方ない」と捉えず、睡眠の構造そのものを守る支援が必要です。
Q3:睡眠薬を使って眠らせるのは、せん妄予防として効果的ですか?
薬剤による“眠らせる”アプローチは、せん妄を悪化させる危険性が高く、慎重な検討が必要です。
特にベンゾジアゼピン系(ジアゼパム、ロラゼパム等)は、GABA作動による中枢抑制により逆に混乱・せん妄・運動制止を引き起こすリスクがあります(Sanchez et al., 2021)。
一方、**メラトニン受容体作動薬(ラメルテオン)や、非ベンゾ系短時間型薬(スボレキサント)**は概日リズムの補正・入眠誘導に有効とされる研究がありますが、非薬物的介入(光・音・活動)との併用が必須です。
睡眠薬は“眠気を起こす”のではなく、“眠れる身体条件”を整えたうえで最小限に使うのが理想です。
Q4:昼夜逆転を防ぐために最も有効なアプローチは?
「夜に寝かせる」より「昼に起こす」を最優先とするのが、リズム調整の鉄則です。
ヒトの体内時計(概日リズム)は、
・朝の光
・日中の活動
・一定の食事タイミング
・社会的刺激(会話、表情、音)
によって調整されています。
これらが乏しいと、夜になっても脳が“夜である”と認識できず、夜間覚醒・せん妄・昼夜逆転の連鎖を招きます。
特に効果があるのは以下の3点。
- 朝の高照度光(2500 lx)でメラトニン抑制と覚醒促進
- 日中の身体活動または座位姿勢の確保
- 日中の“社会的刺激”を意識的に挿入する(会話・音・映像など)
“睡眠介入”は夜だけの話ではありません。
日中の覚醒をどれだけ演出できるかが、夜の質に直結します。

\書籍はWEBで購入可/

\睡眠オタのYouTubeチャンネル/

\どんな活動してるの?/

参考文献
Flannery KB. Sleep Med 2016
Watson PL. Crit Care 2012
Al-Aama T. JAMA Intern Med 2011
Sanchez M. Intensive Care Med 2021