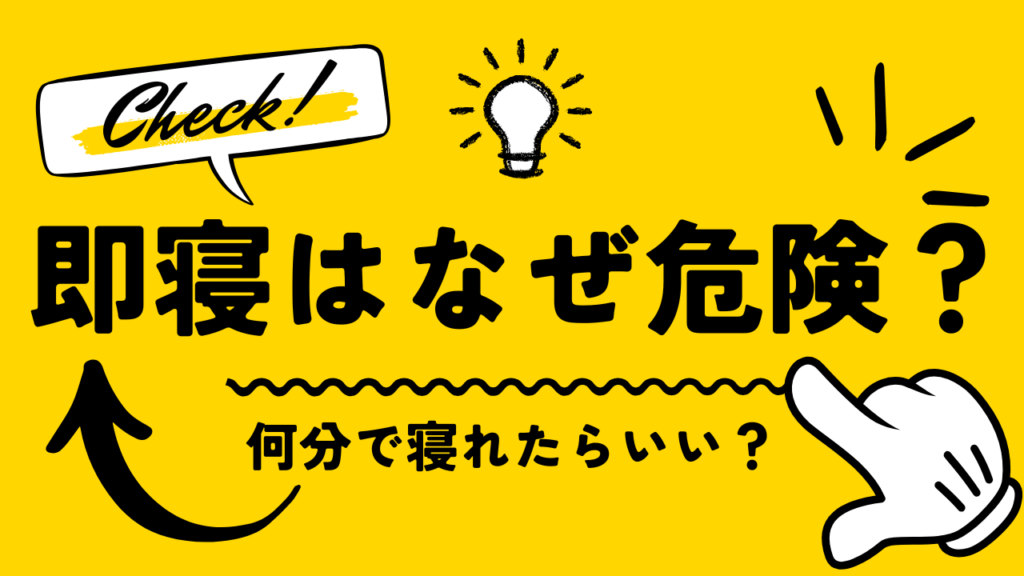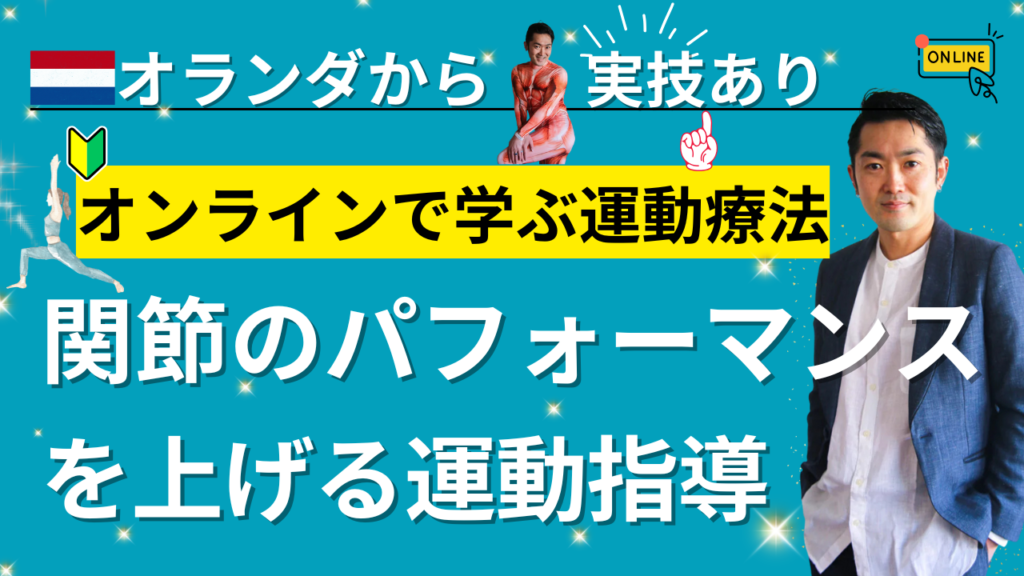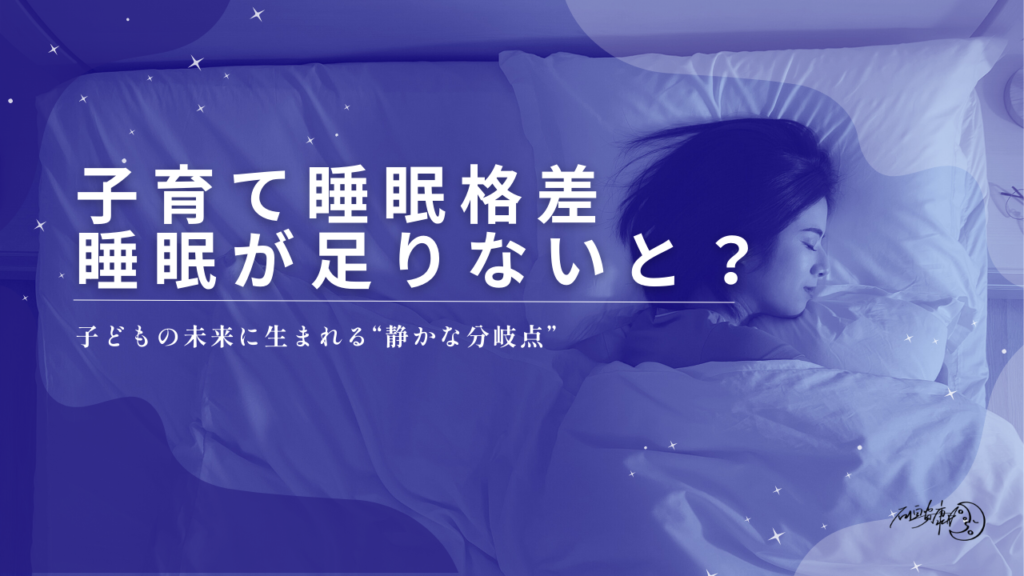「10時間寝たのにスッキリしない」
「寝ても寝ても眠い。何かの病気?」
そんな経験、ありませんか?
「たくさん寝た=体に良い」と思われがちですが、
実は長く寝すぎると体に負担がかかることもあるんです。
今回は、
「なぜ長く寝すぎるのか?」
「寝すぎると何が起きるのか?」
「どうしたらちょうどよく眠れるのか?」
この3つを、睡眠オタク視点でわかりやすく解説します!
🧠 長く寝すぎてしまう5つの理由
① 睡眠不足の“借金返済中”
平日に寝不足が続くと、体は「足りない分を取り返そう」とします。
これは反跳性睡眠と呼ばれる自然な反応。
ただし、土日に寝だめしすぎると、体内時計がズレて夜眠れなくなることも。
📝豆知識
6時間睡眠を5日続けると、約1日の睡眠が不足します。
それを一気に寝だめしても、脳は完全には回復しません。
② 心と体のSOS(うつ・自律神経の乱れ)
「気力が出ない」「布団から出たくない」
それ、もしかしたらうつ状態や自律神経の乱れかもしれません。
精神的なストレスや不安が強いと、長く寝ようとする傾向が出ます。
特に「朝が苦手」「予定がない日は何時間でも寝てしまう」という人は要注意。
③ 血糖値の乱高下で眠気が増す
甘いものや炭水化物を多くとった翌日、血糖値が急に下がると、体はだるくなり「もっと寝たい」と感じます。
つまり、「眠気」ではなく、血糖コントロールの問題かもしれません。
📝豆知識
夜にアイスや菓子パンを食べて寝ると、翌朝起きられないのは血糖スパイクが関係しています。
④ 睡眠の“量”はあるけど“質”が悪い
たとえば、
- いびきをかいている
- 夜中に何度も目が覚める
- 寝汗がすごい
そんな人は、睡眠時間が長くても浅い眠りしか取れていない可能性があります。
特に**睡眠時無呼吸症候群(SAS)**などが隠れていることもあります。
⑤ 現実から逃げたい気持ちがある
仕事、人間関係、将来への不安…。
そんなストレスから「寝てしまえば楽」と、眠りに逃げ場を求めてしまうこともあります。
これは「回避性過眠」と呼ばれ、心のサインです。
寝ても寝ても疲れが取れないと感じたら、心の声に耳を傾けてみてください。

⚠️ 寝すぎによる3つのリスク
① 頭痛・重だるさ
寝すぎると血流が悪くなり、片頭痛や倦怠感を引き起こします。
特に後頭部の重だるさや首こりとセットになることも。
② 自律神経が乱れてしまう
長時間眠ることで交感神経と副交感神経のバランスが崩れ、
・だるい
・食欲がない
・集中できない
など、日中のパフォーマンス低下につながります。
③ 夜、逆に眠れなくなる
「たっぷり寝たのに夜眠れない」
→それ、寝すぎで体が“夜モード”に入れなくなっているかも。
体内時計は朝起きてから約15時間後に眠気を感じるよう設計されています。
昼まで寝ると、夜の眠気が来ないのは当然です。
🌞 どうすれば“寝すぎ”を防げる?
✅ 休日の起きる時間は「いつも+90分以内」
平日と2時間以上ずれると、体内時計がズレて月曜がつらくなります。
「+90分以内」がおすすめ!
✅ 起きたらまず“光”と“動き”
カーテンを開けて、太陽の光を浴びましょう。
そのあと、軽くストレッチ。これだけで脳が「朝だ!」とスイッチオン。
✅ 朝イチのコーヒーはちょっと待って
起きてすぐはコルチゾール(覚醒ホルモン)が分泌されています。
カフェインは1時間後がベスト。
✅ 昼寝は15分〜30分まで
疲れたら昼寝もOK!でも長すぎると夜の眠りを妨げるので注意。
🔍 よくある質問(FAQ)
Q. 土日だけ長く寝るのは問題ないですか?
A. 一時的な「寝だめ」は可能ですが、毎週繰り返すと体内時計が乱れやすくなります。
特に「土日に10時間以上寝て、月曜がつらい」という方は、**“社会的時差ボケ(ソーシャル・ジェットラグ)”**になっているかもしれません。
これは、平日と休日で起床・就寝時間が大きくズレることで、睡眠リズムが乱れ、平日の眠気・集中力低下・体調不良を引き起こす現象です。
毎日同じ時間に起きるのが理想ですが、どうしても寝たいときは「平日+90分以内」に抑えるのがベストです。
Q. 9時間以上寝るのは体に悪いのでしょうか?
A. 必ずしも悪いとは限りませんが、“9時間以上眠らないとスッキリしない”状態は注意が必要です。
長時間睡眠が常態化している場合、以下のような背景が隠れていることがあります。
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)などの睡眠障害
- 抑うつ・慢性疲労・甲状腺機能低下などの体調不良のサイン
- 睡眠の「質」が悪いために「量」で補おうとしている状態
逆に、8〜9時間の睡眠で日中元気に過ごせているなら問題ありません。
大切なのは「何時間寝たか」よりも「起きたときにスッキリしているかどうか」です。
▼参考記事▼
8時間以上寝る人の末路|健康リスクと原因・改善策を徹底解説|精神科特化!訪問看護コラム「くるみのアトリエ」
Q. 昼寝で寝すぎの調整はできますか?
A. 昼寝は短時間なら効果的ですが、“寝すぎのリカバリー”にはなりません。
昼寝には以下のような効果があります:
- 集中力・注意力の回復(NASAの研究では26分の昼寝で34%パフォーマンス改善)
- 自律神経の安定(ストレスホルモンを一時的にリセット)
ただし、30分以上の昼寝は深い眠りに入りやすく、起きたときにぼんやり感(睡眠慣性)が出やすくなります。
また、夕方以降の昼寝は夜の入眠を妨げることがあるため、昼寝は14時まで・20分以内がベストです。
昼寝はあくまで“日中のパフォーマンスを保つ補助策”であり、根本的な睡眠リズムの乱れや睡眠負債の解消にはなりません。
長く寝すぎている人はまず夜間の睡眠の質と生活習慣を見直すことが必要です。
▼2026年!「お伊勢さん」特別企画!!▼


\ 最新の記事をスワイプ👆⇒ /
布団に入ってすぐ寝る人は要注意?「即寝」がよくない本当の理由を医療視点で解説
【オンラインで学ぶ運動療法】関節のパフォーマンスを上げる運動指導
正常運動と異常運動を「体感」して、明日から“説明して介入できる”PTへ こちらはオンラインセミナーのご案内になります。 対象は、 理学療法士・作業療法士 運動療法に携わる方 初心者大歓迎 こんな方にお…
運動と睡眠は切り離せない。 機能改善の鍵は“関係性”にあった。PT/OT向けセミナー
こちらの記事は ・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 対象となるオンラインセミナーのご案内です。 ●こんな悩みありませんか? ☑寝不足でパフォーマンスが安定しないクライアントがいる☑運動指導しても…
寝不足で育つ子の見えない格差|睡眠時間が足りないと何が起きる?子どもの未来に生まれる“静かな分岐点”
【リハ職向け】予防視点のリハ睡眠──施術効果が続く身体づくりのためにできること──
🔍こんな悩み、ありませんか? ☑ 施術・トレーニング後は良いのに、すぐ元に戻る人がいる☑ 可動域や動作の改善が、翌日には低下してしまうことがある☑睡眠ってそもそもどう評価していいかわからない☑ 睡眠の…
ノンレム睡眠からステージ4が消えた理由|深睡眠は減った?分類変更を科学的に解説

📝 まとめ
・寝すぎる理由は「不足の返済」「心と体の不調」「眠りの質の低さ」などがある
・寝すぎは頭痛・だるさ・不眠を引き起こす
・朝の光・運動・生活リズムが「眠れる体」づくりのカギになる
▼気になる記事5選▼

\書籍はWEBで購入可/

\睡眠オタのYouTubeチャンネル/

\どんな活動してるの?/