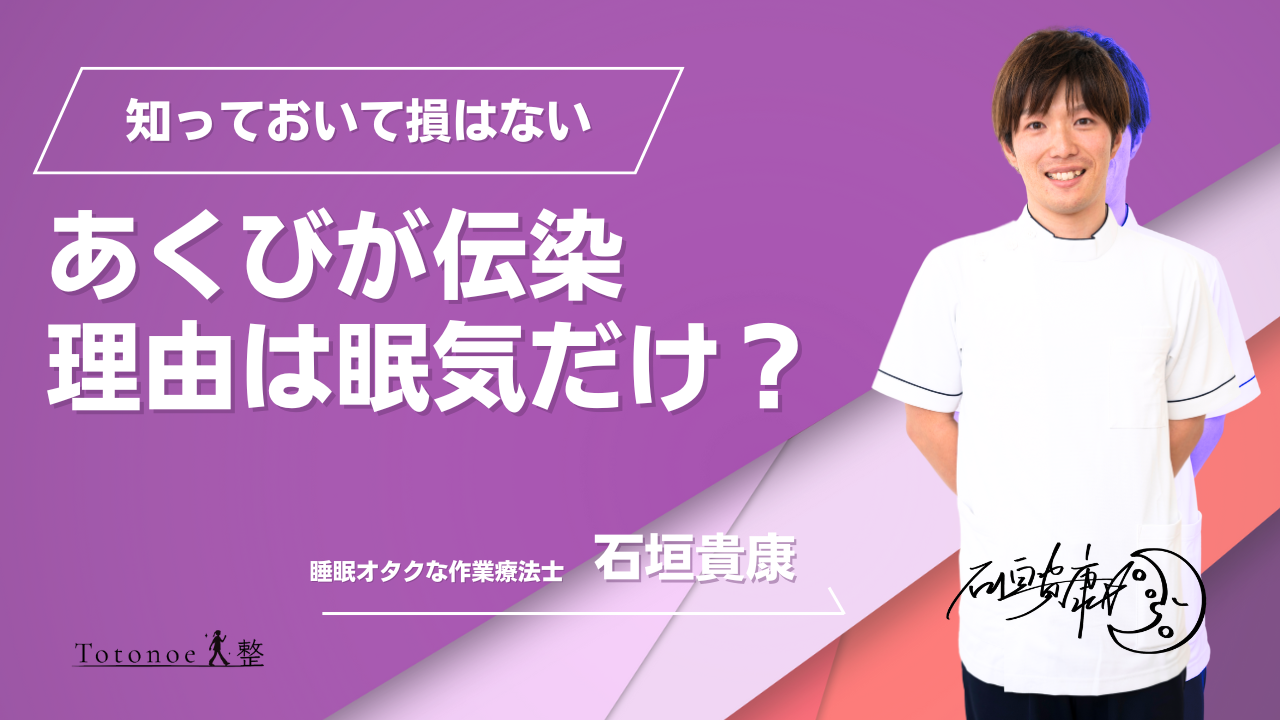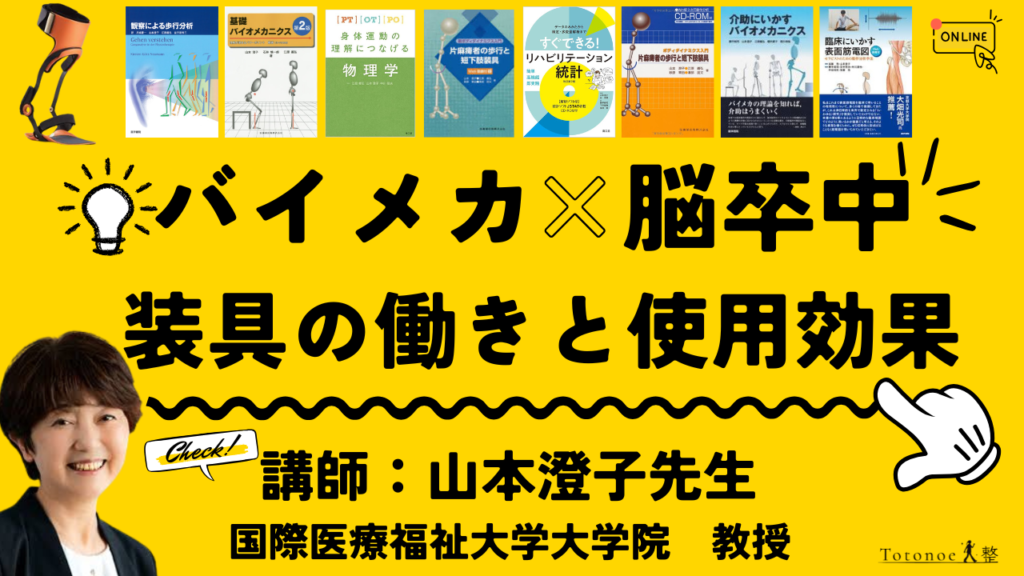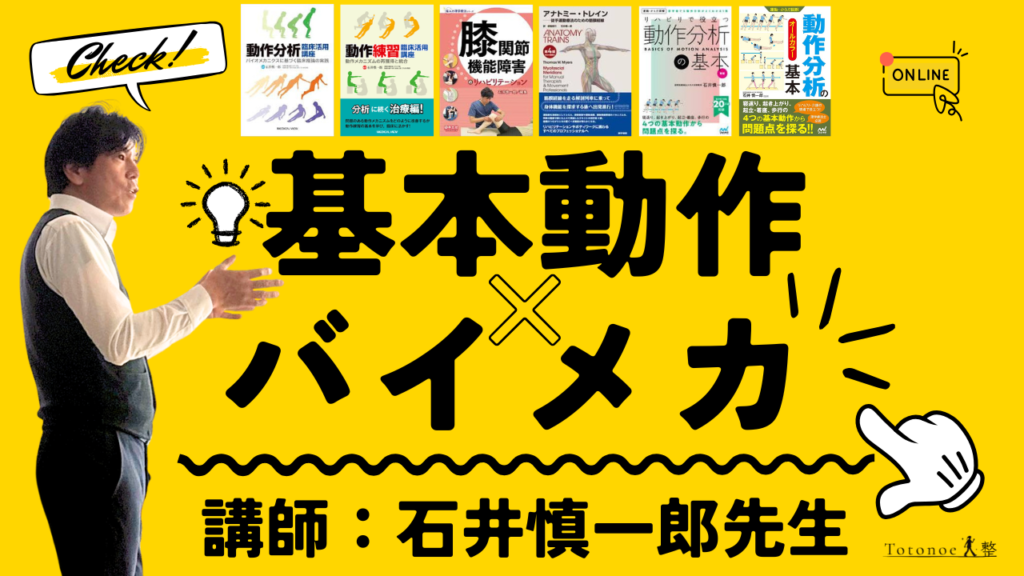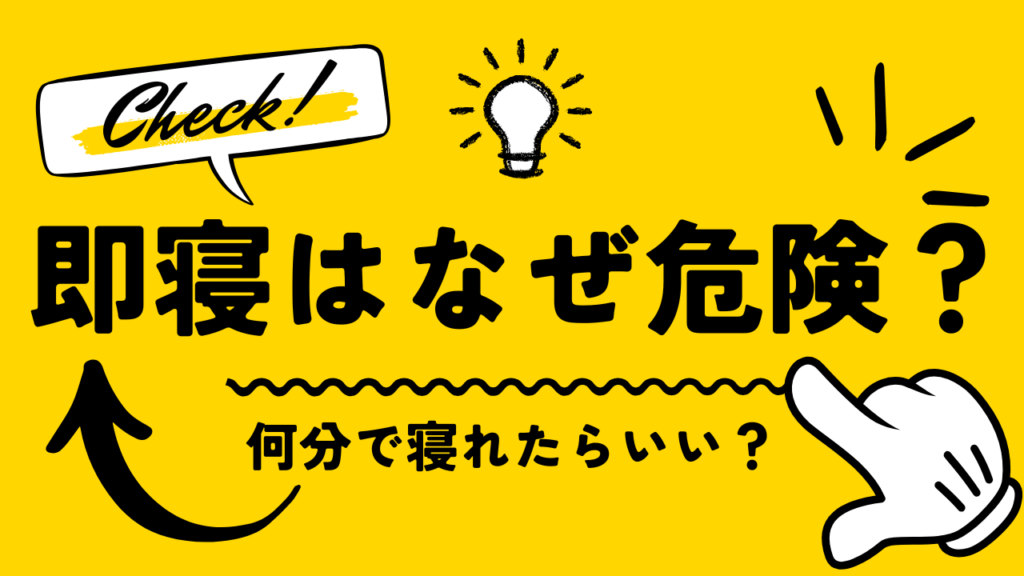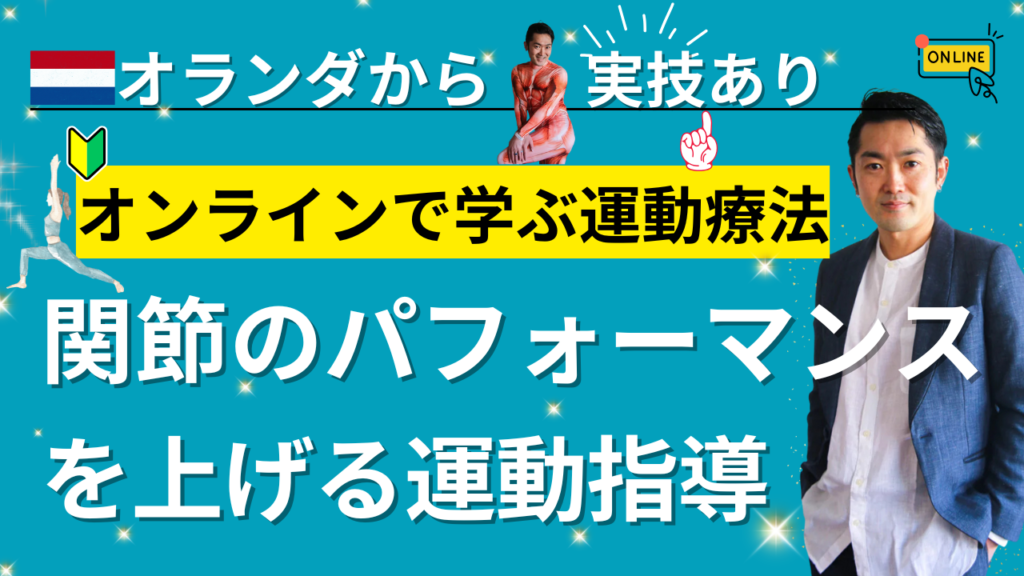目次
はじめに
「あくびが伝染する」という現象を一度は体験したことがあるのではないでしょうか。
隣の人があくびをした途端、自分もつられてあくびをしてしまう。
これは単なる偶然ではなく、科学的なメカニズムが関与しています。
本記事では、睡眠オタクな作業療法士としての視点から、この現象を深掘りし、最新の研究結果も交えながら解説していきます。
この記事を読み進んでいくだけでも「あくび」がでるかも?です。

あくびの役割とは?
あくびは単なる「眠気サイン」ではありません。その役割は多岐にわたり、以下のような仮説が考えられています。
脳の温度調節
あくびをすると深呼吸を伴うため、体内に新鮮な空気が取り込まれ、脳の温度が下がるとされています(Gallup, 2010)。このメカニズムにより、脳の覚醒度が一時的に上昇します。
私は作業療法士として、脳卒中の方のリハビリをしていると「あくび」が病気になってから増えた。という声もよく聞きます。
酸素供給の増加
長時間の低活動状態では、酸素供給が滞ることがあります。あくびをすることで酸素が補充され、体内のバランスが回復します(Provine, 1986)。
緊張緩和と覚醒
あくびは副交感神経を刺激することでリラックス効果をもたらす一方、交感神経を活性化して覚醒状態を促します(Guggisberg et al., 2010)。
あくびがリラックス(副交感神経)と覚醒(交感神経)の両方に影響を与える理由は、体が「適度な覚醒状態」を保つためと考えられています。
- 集中力が低下した場面でのリフレッシュ: リラックスしつつも覚醒を促すことで、集中力が低下した状態から回復します。
- 睡眠前後の調整: 眠気を感じる際にはリラックス効果が優位に働き、覚醒が必要な場面では交感神経が優位に働くため、状況に応じた適応が可能になります。

あくびが伝染する理由
1. 共感能力の影響
あくびが伝染する現象は、人間の「共感能力」と密接に関係しています。研究によると、他人のあくびを見ることでミラーニューロンが活性化され、自分もあくびを引き起こすという仕組みがあることが示されています(Platek et al., 2003)。
2. 社会的つながりの深さ
あくびの伝染率は、他人との「心理的な距離感」によって変化します。たとえば、親しい家族や友人があくびをする場合、その伝染率は高くなります。
一方で、他人や知らない人のあくびでは影響が少ないことが知られています(Norscia & Palagi, 2011)。
3. 進化的な理由
進化の過程で、あくびの伝染は「集団行動の同期」を目的として発展した可能性があります。たとえば、群れで生活する動物において、集団全体が同じタイミングで休息や活動を始めることは、生存率を高める上で有利です(Guggisberg et al., 2010)。
あくびの伝染に関する研究
研究事例1: 動物とあくびの伝染
チンパンジーや犬などの動物にも、あくびが伝染する現象が確認されています。特に犬は飼い主のあくびに反応しやすいことから、動物間でも共感能力が存在することが示唆されています(Joly-Mascheroni et al., 2008)。
研究事例2: あくびの伝染と脳波
ある研究では、他人のあくびを観察する際に脳の「前頭前皮質」が活性化することが確認されました。この部位は感情や社会的認知に関与しており、伝染性のあくびと密接に関連していると考えられます(Schürmann et al., 2005)。

あくびが伝染しない場合
一方で、すべての人が他人のあくびに反応するわけではありません。あくびが伝染しにくい要因として、以下が挙げられます。
- 自閉スペクトラム症(ASD)
ASDを持つ人々では、共感能力やミラーニューロンの働きが異なるため、あくびの伝染が起こりにくいことが報告されています(Senju et al., 2007)。 - 疲労やストレス
強い疲労やストレス下では、他人の行動に注意を向ける余裕が減少し、あくびが伝染しにくくなる場合があります(Provine, 1986)。
睡眠とあくびの関係
あくびは睡眠不足のサインとしても捉えられることが多いですが、必ずしもそうではありません。
しかし、慢性的な睡眠不足は、あくびを引き起こす頻度を増加させる可能性があります。また、あくびが多い場合、以下のような睡眠の質に関する問題が隠れているかもしれません。
- 夜間覚醒が多い
- 睡眠時無呼吸症候群
- 日中の過度な眠気(EDS)

\ 最新の記事をスワイプ👆⇒ /
なぜ睡眠薬を飲み続けても不眠は治らないのか?|効かない本当の理由を作業療法士が解説
保護中: 山本澄子先生セミナー受講生専用 ※3/31まで
保護中: 石井慎一郎先生セミナー受講生専用 ※3/31まで
布団に入ってすぐ寝る人は要注意?「即寝」がよくない本当の理由を医療視点で解説
【オンラインで学ぶ運動療法】関節のパフォーマンスを上げる運動指導
正常運動と異常運動を「体感」して、明日から“説明して介入できる”PTへ こちらはオンラインセミナーのご案内になります。 対象は、 理学療法士・作業療法士 運動療法に携わる方 初心者大歓迎 こんな方にお…
運動と睡眠は切り離せない。 機能改善の鍵は“関係性”にあった。PT/OT向けセミナー
こちらの記事は ・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 対象となるオンラインセミナーのご案内です。 ●こんな悩みありませんか? ☑寝不足でパフォーマンスが安定しないクライアントがいる☑運動指導しても…

まとめ
あくびが伝染する理由は、「共感能力」「ミラーニューロン」「進化的要因」など、複数の要因が絡み合っています。
この現象を通じて、人間の脳や社会性、睡眠との関わりを改めて感じることができます。
あくびが多い場合は、睡眠環境や生活習慣を見直すサインかもしれません。
睡眠オタクな作業療法士としての視点で、日常の「動き」と「休息」をバランスよく取り入れることの重要性を改めて提案します!
▼気になる記事7選▼
参考文献
- Gallup, A. C. (2010). Why do we yawn? Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 34(8), 1267-1276.
- Provine, R. R. (1986). Yawning as a stereotyped action pattern and releasing stimulus. Ethology, 72(2), 109-122.
- Platek, S. M., Critton, S. R., Myers, T. E., & Gallup, G. G. (2003). Contagious yawning: The role of self-awareness and mental state attribution. Cognitive Brain Research, 17(2), 223-227.
- Norscia, I., & Palagi, E. (2011). Yawn contagion and empathy in Homo sapiens. PLoS ONE, 6(12), e28472.
- Joly-Mascheroni, R. M., Senju, A., & Shepherd, A. J. (2008). Dogs catch human yawns. Biology Letters, 4(5), 446-448.
- Schürmann, M., et al. (2005). Yearning to yawn: The neural basis of contagious yawning. NeuroImage, 24(4), 1260-1264.
- Senju, A., Maeda, M., & Kikuchi, Y. (2007). Absence of contagious yawning in children with autism spectrum disorder. Biology Letters, 3(6), 706-708.